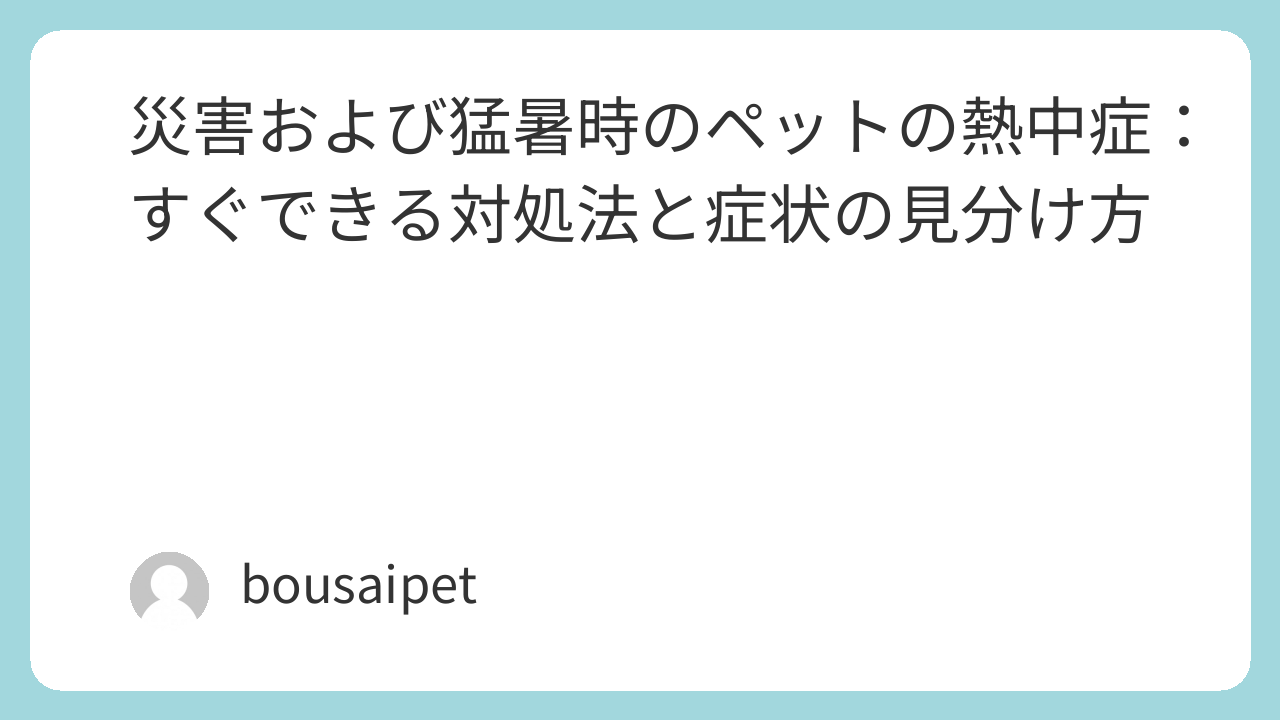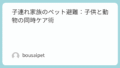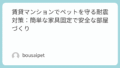地震や台風、洪水などによる停電、あるいは猛暑の環境下においては、ペットが熱中症になるリスクが大幅に高まります。犬や猫は人間より体温調節が苦手なため、熱中症で命を落とす危険性さえあります。素早く症状を見極め、正しい対処をすることが、ペットを守る鍵となります。
この記事では、災害及び猛暑時にペットの熱中症にすぐ対応する方法、症状の見分け方、家庭でできる応急処置、予防するための準備をわかりやすくお伝えしていきます。
災害や猛暑でのペット熱中症の危険性
人間は汗をかいて体温を下げられますが、犬や猫は主にハアハアと息をすることで熱を逃がします。停電でエアコンが止まったり、猛暑の屋外で湿度が高まると、この仕組みがうまく働かず、体温が急上昇してしまいます。2023年の台風被害では、避難中の車内や避難所でペットの熱中症が増え、獣医師への負担も大きかったと報告されています。猛暑の夏日でも、散歩中のアスファルトの熱でペットが具合を悪くするケースも増えているそうです。事前に必要な知識と準備をしておけば、こうした状況でもペットを守ることができます。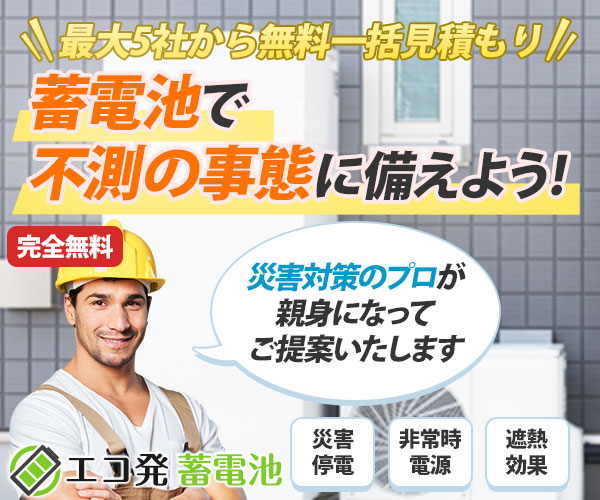
1-1. なぜ災害や猛暑で熱中症が起こる?
災害時は、避難所のエアコン不足、屋外の強い日差し、家内や車内の閉鎖空間がペットの体温を上げることになります。猛暑では、気温35℃を超える日やアスファルトの表面温度(50℃以上)が危険度を増しています。湿度60%以上だと、ペットの呼吸による冷却効果が落ち、熱中症リスクが急増することが判っています。特に、鼻の短い犬(パグ、ブルドッグ)、高齢ペット、太めのペットは注意が必要です。パグの場合、鼻腔が狭いため呼吸で熱を逃がしにくく、たった10分間の高温暴露で症状が出ることがあるそうです。90分以内の対応が命を左右することになります。

1-2. 熱中症の仕組みと影響
熱中症は、体温が上がりすぎて脱水が進むことで起こります。初期は軽い不調ですが、放置すると心臓や腎臓にダメージを与え、最悪の場合、命を落とすこともあります。日本気象協会によると、夏のペット熱中症の病院受診は前年比20%増で、災害時の二次被害や猛暑の日常リスクとして問題になっているそうです。
1-3. 飼い主の役割
飼い主はペットの普段の様子を知っているからこそ、異常を早く見つけることができます。災害や猛暑時の熱中症でも、簡単な対処法を覚えておけば、落ち着いて対処することができます。たとえば、ペットの体温や呼吸数を普段から記録しておくと、異常のサインに気づきやすくなります。
1-4. ペットの種類ごとのリスク
犬:
短頭種(パグ、フレンチブルドッグ)は呼吸が浅く、熱中症になりやすいと言われています。大型犬(ゴールデンレトリバー)は体表面積が大きく、熱をため込みやすくなります。
猫:
口呼吸が少なく、ぐったり感や食欲不振が初期サインになります。長毛種(ペルシャ猫)は熱がこもりやすくなります。
小動物(ウサギ、ハムスター):
体温調節が弱く、気温30℃以上で急速に危険度が増します。
鳥:
羽毛で熱がこもり、熱のストレスで呼吸が乱れてしまいます。
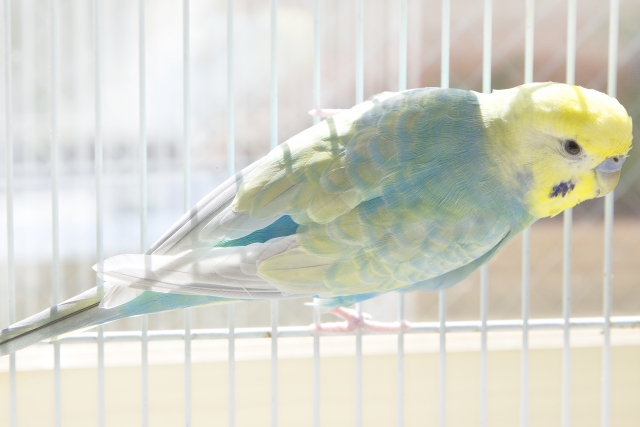
ペットの熱中症の症状を見分ける
熱中症の症状は進行度によって異なり、早期発見が重要になってきます。以下のチェックリストを参考に、ペットの様子をしっかり観察するようにしましょう。犬と猫で症状は似ていますが、猫は口呼吸が少なく、ぐったり感が目立つことがあります。
2-1.初期のサイン
激しい息遣い:
運動していないのにハアハアが止まらない。犬は舌を出し、猫は口を少し開ける。
よだれが多い:
口の周りが濡れて、床にポタポタ落ちる。
耳や足の裏が熱い:
触ると熱く、体温が39℃を超えている。
元気がない:
いつも活発なのに動かず、目を細める。
これらのサインは、災害時の車内や避難所の暑い環境、猛暑の散歩でよく見られます。気温28℃以上、湿度60%以上なら特に注意が必要です。
2-2. 中程度の症状
嘔吐や下痢:
お腹の調子が悪くなり、脱水が進む。
ふらつきやぐったり:
体に力が入らず、横になる。
意識がぼんやり:
名前を呼んでも目を合わせない。

この段階で対応しないと、症状が悪化します。体温計で直腸温を測り、40℃を超えていたら病院に連れていきましょう。猫では嘔吐が早く出ることがあり、注意が必要です。
2-3. 重症のサイン
痙攣や血便:
神経や内臓にダメージが出る。
呼吸が苦しそう、意識がない:
すぐに治療が必要。
重症の場合は、応急処置をしながら獣医師に連絡します。死亡率は50%を超える可能性があり、90分以内の対処が必要になります。
2-4. 症状を見分けるコツ
普段からペットの様子を観察しておくと、異常がわかりやすくなります。安静時の呼吸数(犬:20~30回/分、猫:20~40回/分)をメモし、変化に気づけるようにしましょう。
アプリ「ペット健康メモ」などで体温や行動を記録しておくと便利です。
2-5. ペットの種類ごとの観察ポイント
犬:
舌の色(赤紫は危険)、耳の熱さ、歩き方のふらつきをチェックします。
猫:
隠れる行動の増加、食欲の急激な低下、目のぼんやり感に注意します。
小動物:
ケージ内の動きが止まる、呼吸が速い、毛が濡れる、などをチェックします。

鳥:
羽を膨らませる、くちばしの開閉が激しい、止まり木から落ちる、などをチェックします。
種類に応じた異常サインを覚えておきましょう。
家庭でできる応急処置
熱中症の疑いがあるときは、まず落ち着いて行動しましょう。以下のステップで対応し、
並行して獣医師に連絡するようにしましょう。
3-1. ステップ1:涼しい場所に移動
ペットを直射日光を避けた涼しい場所(室温25℃以下)に運びます。避難所なら日陰やエアコンがあるエリア、車内なら窓を開けて換気します。猛暑の散歩中なら、木陰や室内へ。移動中は体を支え、転ばないよう気をつけましょう。たとえば、避難所の屋外テントから室内の休憩エリアに移すだけで、体温の下がり具合が違います。
3-2. ステップ2:水を与える
意識がある場合、常温の水を少しずつ(1回50ml程度)与えます。飲まないときは、スポイトやシリンジで口元にそっと入れます。スポーツドリンクは塩分が多いので避けます。氷を舐めさせるのも良いですが、飲み込まないよう注意しましょう。ウサギやハムスターには、スポイトで1滴ずつ慎重に与えましょう。

3-3. ステップ3:体を冷やす
全身に常温の水をかける:
気化熱で体を冷やします。氷水は血管を縮めるので使わないようにしましょう。
首、脇、足の付け根、耳裏に濡れタオルや保冷剤を:
10分ごとに交換します。タオルは水で濡らし、軽く絞って使いましょう。
扇風機やうちわで風を送る:
体の奥の熱を下げます。携帯扇風機が便利です。
体温計で直腸温を測り、39.4℃になったら冷却をやめます。冷やしすぎると体温が下がりすぎるので注意しましょう。鳥の場合、羽を濡らしすぎないよう、霧吹きで軽くスプレーするとよいです。
3-4. ステップ4:獣医師に連絡、病院へ
応急処置をしたら、すぐに動物病院に電話します。症状(例:嘔吐、痙攣)を伝え、指示を仰ぎます。重い症状なら、体を冷やしながら病院へ連れていきます。避難所からタクシーや救急車を使うのも選択肢になります。獣医師会の相談窓口(全国共通)も活用してみましょう。
3-5. 注意点
氷や冷水は使わない:
急に冷やすとショック状態になる可能性があります。
アルコールや冷凍スプレーは禁止:
皮膚を傷める可能性があるので使わないようにしましょう。
軽い症状でも受診:
内臓のダメージが後で出ることもあるので軽い症状でも受診しましょう。

体温計、濡れタオル、保冷剤、スポイトを用意しておきましょう。小動物や鳥用に、小型のスポイトや霧吹きを準備しましょう。
災害や猛暑の予防:熱中症を防ぐ準備
応急処置は最終手段です。災害や猛暑時の熱中症を防ぐ準備をしておくのが大事です。
4-1. 避難や猛暑時の環境を整える
避難所では日陰スペースを確保し、ペット用に水を常時用意しておきます。猛暑の散歩では、朝6時や夕方7時以降の涼しい時間を選び、アスファルトを避けましょう。湿度が高い日は、通気性の良いキャリーや除湿シートを使うと良いです。たとえば、折りたたみキャリーは空気が通りやすく、猫や小動物に適しています。
4-2. 普段の体調チェック
ペットの体温を定期的に測り、普段の状態を把握しておきます。鼻の短い犬や高齢ペットは、気温30℃以上で外出を控え、室内を25℃に保ちます。アプリ「ペット体温記録」などでデータを管理しておくと、災害や猛暑時の比較がしやすくなります。毎週末に体温と呼吸数を記録する習慣を身につけるとよいです。
4-3. 家族で役割を分担する
家族で熱中症チェックの担当を決め、災害や猛暑時に1人がペットの様子を見れるようにします。子供がいる場合、「ペットの耳を触って熱いか見て」と教えると、協力しやすくなります。10歳以上の子供なら、水ボトルを管理する役割を任せても良いですね。
4-4. 準備しておくグッズ
冷却タオル:
水で濡らして首に巻きます。100円ショップでも購入可。
携帯水ボトル:
避難や散歩中の水分補給に使います。500mlサイズが便利です。
応急キット:
体温計、消毒液、ガーゼ、スポイト、霧吹き。
遮光シート:
避難所のテントや車に貼り、日差しをカットします。
4-5. ペットの種類ごとの予防策
犬:
猛暑では短時間の散歩にし、首に冷却タオルを巻きます。短頭種は特に注意が必要です。
猫:
キャリー内に通気孔を確保し、隠れ場所(タオル)でストレスを軽減させます。

小動物:
ケージに保冷剤を置き、換気を徹底します。
鳥:
ケージを直射日光から守り、霧吹きで湿度調整します。
早わかり表:熱中症の症状と対処法
| 進行度 | 主な症状 | 対処法 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 初期 | 激しい息遣い、よだれ、耳熱 | 涼しい場所へ、水を少量 | 体温測定、獣医師連絡 |
| 中程度 | 嘔吐、下痢、ふらつき | 常温水かけ、濡れタオルで冷却 | 氷水NG、10分ごと交換 |
| 重症 | 痙攣、意識低下 | 全身冷却、すぐ病院へ | 90分以内受診、冷やしすぎ注意 |
まとめ:すぐできる対処法でペットを熱中症から守る
災害や猛暑時のペットの熱中症は、素早く症状を見極め、適切な対処をすることが重要です。激しい息遣いやよだれに気づいたら、涼しい場所への移動、水分補給、体を冷やすことを心がけましょう。また、グッズを用意しておくことも大切です。まずは以下のポイントを参考に、対応出来るようにしておきましょう。
症状をチェック:
普段の観察で異常を早く見つけられるようにしておく。
すぐ対処:
ステップを守り、すぐ獣医師に連絡する。