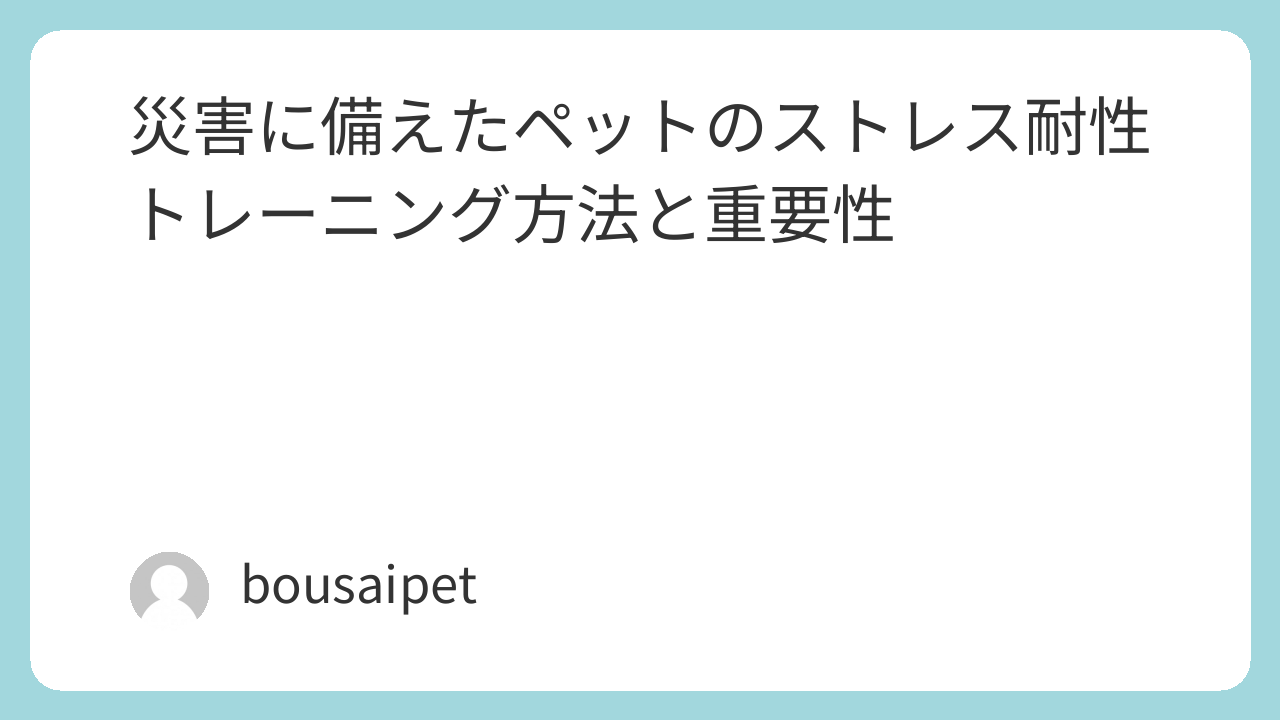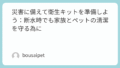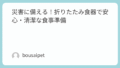日本は地震、台風、洪水など、突然の災害が起こりやすい国ですが、ペットはその時にパニックになったり体調を崩したりすることがよくあります。普段からストレスに慣れさせておけば、ペットも落ち着いて過ごす事ができ、それが、家族みんなの安心にもつながります。
この記事では、犬、猫、爬虫類、鳥が災害時に慌てずに対応できるように、日常でできるトレーニングをわかりやすくご紹介していきます。
ペットのストレス耐性トレーニングの大切さと必要性
災害は突然やってきて、ペットに大きなストレスを与えます。事前にトレーニングをしておけば、ペットが落ち着いて行動でき、飼い主さんの指示にも従いやすくなります。この章では、なぜトレーニングが必要なのか、しないとどんなリスクがあるのかを詳しくお伝えしていきます。
1-1. なぜストレス耐性トレーニングが必要なの?
災害では、大きな揺れや騒音、避難所での特殊な環境がペットを不安にさせてしまいます。たとえば、2016年の熊本での大きな地震では、避難の混乱でペットがパニックになり、キャリーから飛び出したケースがあったそうです。トレーニングを事前にしておけば、ペットはそんな状況でも落ち着いていられ、飼い主さんともコミュニケーションを取る事ができます。たとえば、犬がキャリーバッグ内でリラックスできるようになれば、避難所生活でもストレスを減らす事につながります。
1-2. トレーニングしないとどんなリスクがある?
トレーニングをしていないと、災害時にペットがパニックを起こして逃げ出したり、過度のストレスにより攻撃的になったりする可能性があります。2020年の九州での豪雨では、訓練不足の猫が避難所で隠れて出てこなくなり、ご飯を食べずに弱ってしまった事例がありました。主なリスクは次の通りです。
(1)パニックで逃げたり怪我したりする。
(2)ストレスでご飯を食べなくなり病気にかかる。
(3)避難所でのトラブルで家族の心の負担が増える。
*トレーニングしていないペットは、災害時に体調を崩す確率が2倍以上高いと言われています。犬が騒音に慣れていないと、避難所でずっと吠えてしまうこともあるそうです。

1-3. ペットの種類ごとのストレス
ペットの種類によって、ストレスへの反応はいろいろです。犬は大きな音に驚いて吠えたり走り回ったりするようになります。猫は環境が変わると隠れて動かなくなることが多いです。爬虫類は温度や湿度の変化に弱く、鳥は小さな音でもビックリしてしまいます。
鳥はケージが揺れると羽を傷めることもあります。

1-4. トレーニングでどんな良いことがある?
トレーニングをしておけば、ペットは災害の混乱でも落ち着いていられ、飼い主さんの指示に従いやすくなります。たとえば、キャリーバッグに慣れた猫は避難所でも静かに過ごす事ができますし、避難所生活におけるトラブルも減ると思います。
ペットのストレス耐性トレーニングの具体的なやり方
毎日できるトレーニングは簡単なので、誰でも始められます。ペットの種類ごとに、効果的な方法をご紹介します。
2-1. 犬のためのトレーニング
犬は騒音や人の多さにビックリしやすいので、環境変化に慣れる練習をしましょう。
キャリーバッグに慣れる:
毎日10分、キャリーバッグに入れて落ち着かせます。おやつをバッグに置いて、ドアを開けたまま慣らすことからスタートしましょう。1週間後、ドアを閉めて、1日5分ずつ時間を増やします。
騒音に慣れる:
ラジオや掃除機の音を小さく流して、落ち着いていたら褒めます。1日5分、2週間続ける。
指示の練習:
「座れ」「待て」を毎日5回、家のいろんな場所でやってみます。災害時に指示に従えるようにします。
模擬避難:
定期的に、キャリーバッグで家の外を歩きます。慣れたら近所の公園まで行ってみましょう。
2-2. 猫のためのトレーニング
猫は環境が変わると不安になりやすいので、安心できる場所を増やす練習をします。
キャリーに慣れる:
キャリーをリビングに置いて、毛布やおやつを入れて居心地よくしてあげます。毎日5分、ドアを開けて慣らす。2週間後にドアを閉めて、10分まで増やします。
環境変化:
週1回、部屋のクッションやカーテンを少し動かして、落ち着くまで見守ります。
人に慣れる:
家族以外の友人に週1回、5分触ってもらう。避難所の人混みに備えます。
移動練習:
定期的に、キャリーで家の周りを10分歩きます。慣れたら車で近所を一周してみましょう。

2-3. 爬虫類のためのトレーニング
爬虫類は温度や湿度の変化に弱いので、環境変化に慣れる練習をします。
ケージ移動:
週1回、ケージを部屋の別の場所に動かして、2時間置いてみます。落ち着いていたらエサをあげる。
温度変化:
ヒーターを1日5分オフにして、徐々に慣らします。
触れ合い:
毎日3分、優しく触ります。
模擬避難:
定期的に、ケージを小さなボックスに移して、10分外に置いてみます。
2-4. 鳥のためのトレーニング
鳥は音や揺れに敏感なので、落ち着く練習を重視します。
ケージに慣れる:
毎日5分、カバーをかけて暗くして落ち着かせます。
音に慣れる:
ラジオを小さく流して、1日5分、徐々に音量を上げてみます。落ち着いたらおやつで褒めます
揺れに慣れる:
ケージを軽く揺らして、毎日3分続けてみます。
移動練習:
定期的に、ケージをカバーで覆って、家の外で10分過ごしてみます。
トレーニングを成功させるコツ
トレーニングを楽しく効果的に進めるためのポイントをまとめてみました。
3-1. ペットのペースを大切に
無理に進めるとペットのストレスになるので、ペットの反応を見ながらゆっくり進めましょう。たとえば、犬がキャリーバッグを嫌がるなら、1分からスタートします。猫が隠れるなら、短い時間でやってみます。
3-2. おやつや褒め言葉で楽しく
おやつや「いい子だね!」でペットをやる気にさせます。犬にはスナック、鳥には好きな種をあげます。毎日少しずつあげて、トレーニングを楽しい時間にしてあげます。
3-3. 進捗をメモ
ノートやスマホに、どんな練習をしたかと、ペットの反応を記録しておきます。たとえば、「キャリーバッグで5分落ち着けるようになった」などとメモします。

災害時のペット対策とトレーニングの組み合わせ
トレーニングを災害準備と組み合わせると、更に効果的です。
4-1. 避難バッグの準備
トレーニングと併せて、5日分のご飯、水、健康メモをバッグに入れておきます。犬や猫はリード、爬虫類は保温パック、鳥用にはカバーを入れておきます。
4-2. 避難ルートをチェック
月1回、トレーニングの一環で避難ルートを歩いてみます。犬をキャリーバッグで、猫をバッグで近所の避難所まで運んでみましょう。
4-3. 避難所のルールを調べる
ペットOKな避難所のルールを事前にチェックします。キャリーバッグが必要なら、トレーニングで長時間慣らしておきましょう。
4-4. 獣医師と相談
トレーニング中に体調が変わったら、すぐ獣医師に相談します。たとえば、爬虫類がご飯を食べないのはストレスかもしれません。

トレーニングの成果を最大化するアイデア
トレーニングをさらに効果的にするための追加のアイデアをご紹介します。
5-1. ご近所との連携
近所のペット仲間と避難計画を共有します。たとえば、避難所でのペットスペースの情報を交換しておきます。
5-2. 季節ごとの調整
夏は暑さ、冬は寒さに慣れる練習をします。たとえば、爬虫類は夏に短時間のヒーターオフを試してみます。
5-3. 遊びを取り入れる
トレーニングを遊びの時間にします。犬にはおもちゃをキャリーバッグに入れ、猫にはキャリーでボール遊びをさせます。
5-4. 長期的な目標設定
3ヶ月ごとに目標を設定します。たとえば、犬がキャリーバッグで30分落ち着ける、猫が知らない人に触られても平気、など。
5-5. ストレスサインの観察
ペットのストレスサイン(犬の震え、猫の隠れ行動など)を毎日チェックします。ノートに記録して、トレーニングを調整します。
5-6. トレーナーとの連携
トレーニングが難しい場合、プロのトレーナーに相談。たとえば、犬の吠え癖はトレーナーのアドバイスで改善できます。
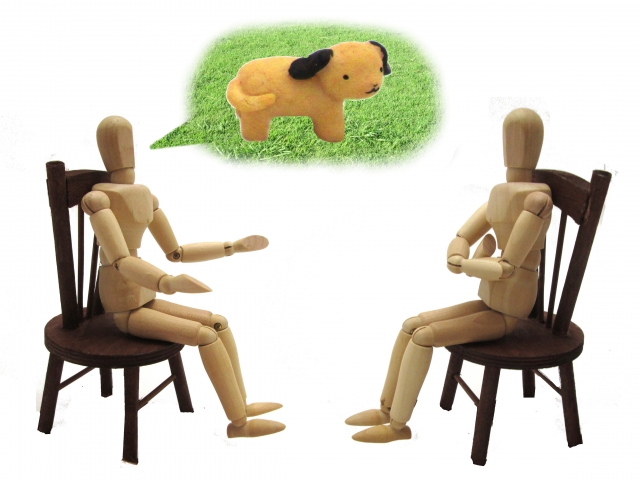
早わかり表:ペットごとのトレーニングのポイント
| ペット | トレーニング内容 | 頻度 | ポイント | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|
| 犬 | キャリーバッグ・騒音・指示 | 毎日5~10分 | おやつで褒める | 2週間で効果 |
| 猫 | キャリー・環境変化 | 週1~2回 | 短時間から | 1ヶ月で慣れ |
| 爬虫類 | ケージ移動・温度 | 週1回 | 温度管理必須 | 2週間で安定 |
| 鳥 | ケージ・音・揺れ | 毎日3~5分 | 優しく揺らす | 1ヶ月で順応 |
まとめ:毎日の耐性トレーニングで災害時でも対応出来るようにしておこう
災害時にペットが落ち着いて行動できるようにする為の、毎日のストレス耐性トレーニングはとっても重要です。さっそく以下のステップから始めていってみましょう。
ペットの反応をチェック:
騒音や環境変化への弱点を把握する。
トレーニング開始:
キャリーバッグや音に慣らす。
毎日続ける:
少しずつ習慣にする。
避難準備:
避難バッグ準備やルート確認を行う。