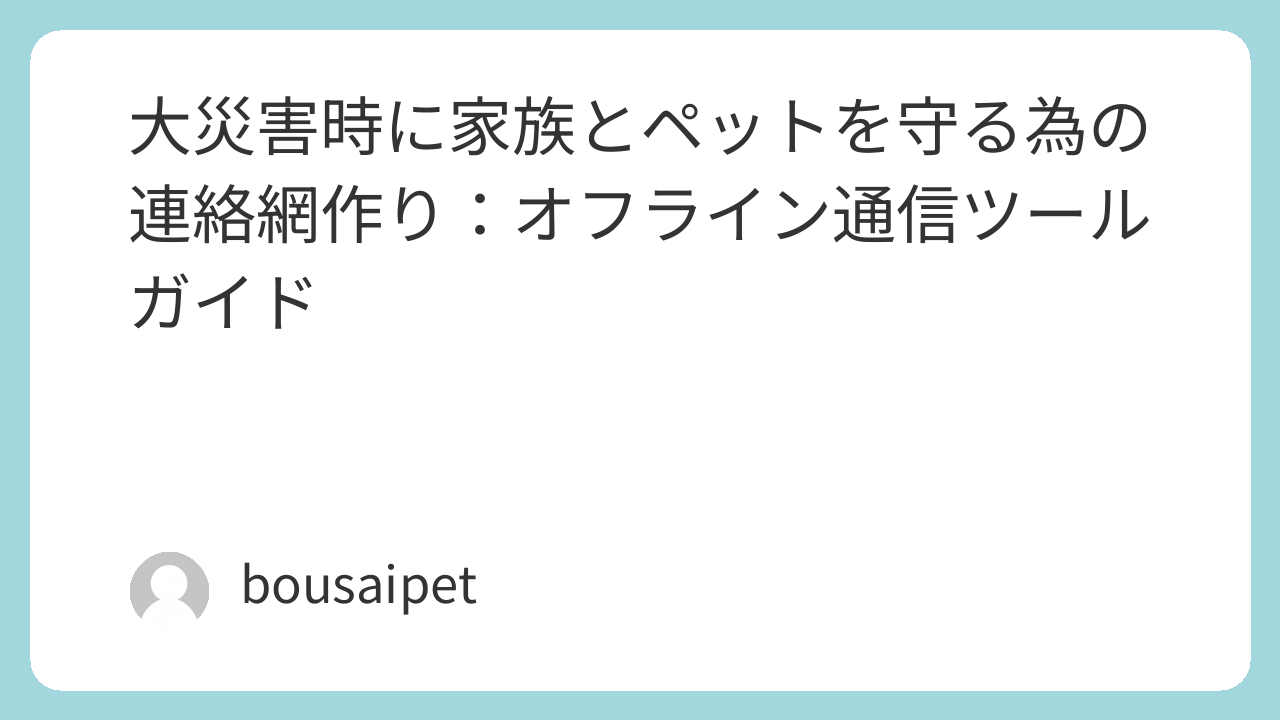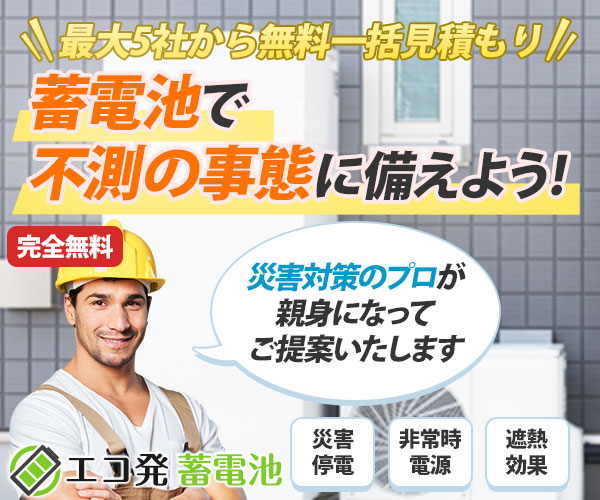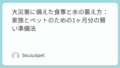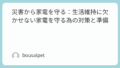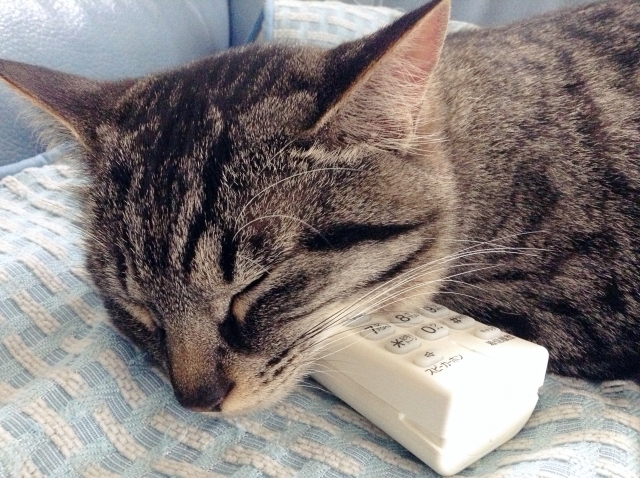
大災害が起きると、電話やネットが使えなくなり、家族との連絡やペットの安全確保が難しくなることが想定されます。この記事では、家族で簡単に作れる連絡網と、ネットがなくても使える通信ツールの準備方法をわかりやすくお伝えしていきます。
災害時の連絡手段の大切さ
大災害が起きると、突然連絡手段が途絶えることがよくあります。2011年の東日本大震災では、携帯電話が使えず、家族の安否確認に時間がかかったケースがたくさんありました。ペットを飼っているご家庭では、飼い主が家族や近隣と連絡を取れないと、ペットが
迷子になったり、避難所での保護が難しくなったりもします。事前に連絡手段を整え、ペットの安全を守る準備をしておけば、もしもの時も落ち着いて対応することができます。
1-1. 大災害で連絡が取れなくなるリスク
災害時には、停電や通信基地局の故障で、電話やネットが使えなくなることが想定されます。総務省のデータによると、震度6以上の地震では、通信が復旧するまでに3~7日かかると言われています。家族が学校や職場などバラバラの場所にいる場合、どこにいるか、どうやって集まるかを決めるのが、非常に難しくなります。ペットの場合、飼い主が家族や近隣と連絡できないと、ケージから逃げ出したペットの居場所がわからなくなったり、
避難所で誰が世話をするか決められなかったりします。
1-2. 連絡手段を準備するメリット
事前に連絡網やオフラインのツールを用意しておくと、災害時の混乱が防げます。家族の安否をすぐに確認できたり、避難場所をスムーズに決められたりできます。ペットにとっても、飼い主の連絡先がわかれば、近隣の人や救助者に預ける時に安心です。日本動物愛護協会によると、迷子のペットの7割は、連絡先がはっきりしないために飼い主と再会できないのだそうです。
1-3. ペットの種類ごとの違い
ペットは種類によって、災害時の行動が違ってきます。犬は飼い主を探して走り回りますし、猫は隠れて見つけにくくなることがあります。爬虫類や鳥はケージが壊れると逃げ出しやすく、飼い主の連絡先がわからないと保護が難しくなります。

家族のための連絡手段の確保
大災害時に家族と連絡を取れるよう、簡単な準備方法をご紹介します。ネットが使えなくても大丈夫な方法と、デジタルツールを組み合わせて、しっかりした連絡網を作りましょう。
2-1. 家族の連絡網
家族全員が知っている連絡網を作ると、災害時の混乱が減ります。
緊急連絡リスト:
家族の電話番号やLINEのIDを紙に書いて、防水ポーチにしまっておきます。
集合場所のリスト:
近くの公園や避難所を2~3箇所決めて、地図を印刷してリストに付けておきます。
予備の連絡先:
親戚や近隣の人の連絡先を追加しておきます。
伝言板の活用:
自治体の伝言ダイヤル(171番、無料)の使い方を家族で確認しておきます。
*連絡リストは、家族のカバンや家のキッチンなど、目立つ場所に置いておきましょう。
子供にもリストの場所を教えておくと安心ですね。
2-2. ネットがなくても使えるツール
電話やネットが使えない時に備えて、オフラインのツールを準備しておきましょう。
トランシーバー:
1~2kmの範囲で使えるトランシーバー(1台5,000円程度)を用意します。災害時は大活躍します。

ホイッスル:
音で居場所を知らせることができます。
メモキット:
防水ノートとペン。避難所で伝言を残す用に使います。
*トランシーバーは、電池を多めに用意しておきます。年に1回、ちゃんと動くか確認しておきましょう。
2-3. デジタルツールの準備
ネットが復旧した時に備えて、デジタルツールも用意しておきましょう。
クラウドに保存:
家族の連絡先や避難計画をGoogle Driveに保存(無料)しておきます。
充電バッテリー:
10,000mAhのバッテリーを用意します。スマホを3回は充電できます。
オフライン地図:
地図アプリ(Maps.me、無料)に避難所を登録しておきます。ネットがなくても使えます。
予備スマホ:
古いスマホ(5,000円程度)をオフライン用に準備します。連絡先や地図を保存しておきます。
*デジタルツールは、停電に備えて充電器も用意しておくとよいでしょう。
2-4. 通信訓練の実施
災害時に慌てないように、家族で連絡手段の使い方を練習しておきましょう。
トランシーバー練習:
30分程度、家族でトランシーバーの使い方を試してみましょう。
ホイッスル練習:
子供にホイッスルの吹き方を教えます。
集合場所確認:
家族で避難場所を歩いて確認してみます。
伝言ダイヤル練習:
171番の使い方を家族で試してみましょう(無料)。

ペットを守る連絡対策
ペットが大災害時に迷子にならないよう、連絡手段や識別方法を準備しておくことが大事です。犬、猫、爬虫類、鳥に合わせた対策をご紹介します。
3-1. ペットの連絡タグと識別準備
ペットが迷子になっても飼い主と再会できるように、識別情報を用意しておきます。
首輪タグ:
ペットの名前と飼い主の電話番号を刻んだタグ。犬や猫には必須。
マイクロチップ:
犬や猫に埋め込んでおきます(5,000円/匹)。獣医師で登録できます。
ケージシール:
爬虫類や鳥のケージに防水シールで連絡先を書いておきます。
ペットの写真:
最新の写真を印刷しておきます。迷子捜索に役立ちます。
IDカード:
ペットの特徴や連絡先をカードにまとめ、ケージに付けておきます。
3-2. 近隣との連絡ネットワーク
近隣の人と協力して、ペットの安全を守りましょう。
近隣リスト:
近隣5軒程の連絡先を紙にまとめて、防水ポーチに保管しておきます。
ペット情報カード:
ペットの種類や名前、連絡先を書いておきます。
LINEグループ:
近隣の人とペットの情報を共有しておきます。緊急時の連絡用として使います。
ペット預かり依頼:
信頼できる近隣の人に、事前に預かりをお願いしておきます。
3-3. ペットのオフライン追跡方法
ネットがなくてもペットの居場所を確認する方法があります。
小さなベル:
犬や猫の首輪に付けるベルになります。音で居場所がわかります。

反射シール:
爬虫類や鳥のケージに貼ります。暗闇でも見つけやすいです。
簡単メモ:
ケージに「飼い主の連絡先」を書いたメモを貼っておきます。
目印布:
ケージに目立つ色の布を結び、遠くから発見しやすくします。
3-4. ペットの連絡訓練
ペットにも簡単な訓練をしておくと安心です。
ベル慣らし:
犬や猫にベルの音を慣らしておきます。
近隣紹介:
ペットを近隣の人に紹介し、顔見知りになっておきます。
連絡網とペット対策を進めるステップ
家族の連絡網とペットの安全対策を進める為の簡単な手順をご紹介します。
4-1. 家族の連絡網を準備
まず、家族の連絡手段を決めておきます。
リストを作る:
家族の連絡先と集合場所を紙に書いて防水ポーチに入れておきます。
ツールを買う:
トランシーバーやホイッスルを購入します。

デジタル系の準備:
クラウドに連絡先を保存し、充電バッテリーを用意しておきます。
練習の計画:
練習しないと忘れる為、定期的に家族で連絡練習をいます。
*リストは家族全員で共有し、玄関やカバンに置いておきましょう。
4-2. 予算を考える
家族4人とペット2匹の連絡対策を5万円以内で揃える場合です。
(価格はあくまで目安です)
連絡網:
リストとポーチで2,000円。
オフライン工具:
トランシーバー2台とホイッスルで1.2万円。
デジタルツール:
充電バッテリーと充電器で4,000円。
ペット対策:
タグ、チップ、ベルで1.5万円。
*予算を3回に分けて、1回1.5万円くらいで進めると無理がありません。
4-3. 定期的に確認する
連絡対策は定期的な見直しが必要です。
3ヶ月ごと:
トランシーバーの電池やタグの状態をチェックします。
年に1回:
連絡先や近隣リストを更新します。
自治体に相談:
災害時の通信支援情報を確認しておきます。

ペット確認:
ペットの成長に合わせてタグやベルを調整します。
早わかり表:連絡網とペット対策
| 項目 | 家族 | ペット | 費用目安 |
|---|---|---|---|
| 連絡網 | 緊急連絡リスト、集合場所 | 近隣リスト、情報カード | 0.5~1万円 |
| オフライン工具 | トランシーバー、ホイッスル、旗 | 小さなベル、反射シール、布 | 1~2万円 |
| デジタルツール | クラウド、充電バッテリー、予備スマホ | マイクロチップ、写真、IDカード | 0.5~1万円 |
| ペット識別 | – | 首輪タグ、ケージシール | 0.3~0.6万円/匹 |
| 確認 | 3ヶ月ごとの点検、訓練 | タグやベルの定期チェック、訓練 | 無料~0.5万円 |
まとめ:家族とペットを守る連絡手段の準備
大災害に備えて、家族の連絡網とオフラインの通信ツール、ペットの安全対策を事前に準備することが大切です。連絡リストやトランシーバー、ペットのタグなどが準備できていれば、もしもの時でも安心できます。以下のポイントを参考に、さっそく今日から準備を始めてみましょう。
連絡網のまとめ:
家族と近隣の連絡先をまとめ、共有しておく。
オフライン手段の準備:
トランシーバーやベルで連絡手段を確保しておく。
ペットの安全:
タグやチップで迷子を防げるようにしておく。