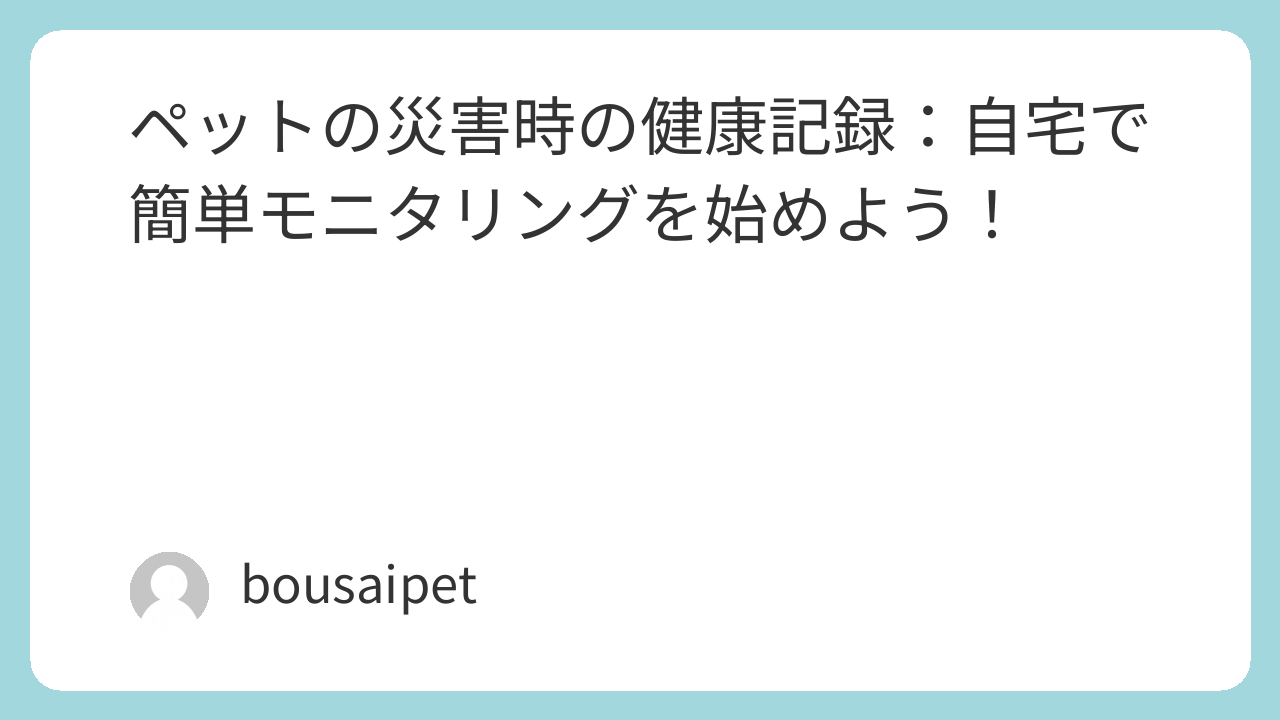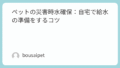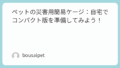ペットを飼う家庭では、災害時の健康記録はペットの状態をしっかり把握し、適切なケアをするための大事なものになります。災害が起こる前には、健康記録を基に予防策を考えておくことで、緊急時の対応がスムーズに行う事が出来ますし、災害が起きた後には、避難生活やストレスで健康が悪化する可能性があるので、事前に記録したデータが獣医師の診察や治療に役立つ可能性があるんです。
この記事では、災害前と災害後の自宅でのペットの健康記録の簡単なモニタリング方法を詳しくお伝えしていきます。
災害時に健康記録が大事な理由
ペットの健康記録は、災害時においてペットの状態を正確に把握し、適切な対応を可能にする大切なツールです。災害が起こる前には、普段の健康状態を記録しておくことで、異常を早く見つけたり、予防策を立てたりでき、緊急時の判断材料になります。たとえば、過去の病気やアレルギーをメモしておけば、避難所での対応がスムーズに進みます。災害が起きた後には、
ストレスや食事の変化で体重が減ったり、消化器に問題が出たりすることが考えられるので、事前に記録したデータが獣医師のサポートに役立ちます。健康記録が不十分だと、適切な治療が遅れてしまい、ペットの回復が難しくなるリスクがあるため、日常的なモニタリングが欠かせません。
健康記録をとる為の準備
2.1 基本情報の記録
ペットの基本的な健康データを集めて、整理しておくことが重要です。
身元情報:
名前、年齢、性別、品種を記録します。マイクロチップがあれば番号も一緒にメモしておくと、行方不明時の識別が楽になります。
過去の病気:
以前の病気や手術、アレルギー情報を詳しく書いておきます。使用した薬の名前や量も忘れずに記載しましょう。
普段の状態:
1か月分の食事量、排泄の回数、睡眠のパターンを記録しておきます。毎日の習慣を表にまとめておくと楽です。

2.2 モニタリングツールを準備
簡単な道具で健康を観察できる環境を整えてみましょう。
体温計:
ペット用のデジタル体温計を用意します。正常な範囲は38~39℃です。
はかり:
体重を週1回測る用に準備します。ペットが乗るのに慣れるよう練習させておくと良いです。
ノートやアプリ:
防水のノートやスマートフォンのアプリを使い、データを管理します。アプリならグラフ機能があるものが便利です。
2.3 定期的な観察スケジュール
健康状態をずっと追える習慣を作りましょう。
週1回チェック:
体重、体温、食欲の変化を毎週確認します。同じ時間帯に測るとデータが安定します。

月1回写真:
毛並みや目、鼻の状態を写真に撮り、目で見てわかる記録を残します。自然光の下で撮ると違いがわかりやすいです。
異常時の記録:
嘔吐や下痢、咳などの症状が出たら、すぐにメモします。日時や状況(例: 散歩後)を一緒に書いておくと後で役立ちます。
2.4 健康記録の保管方法
記録の保管方法になります。
防水袋:
ノートや写真を防水袋に入れて、湿気や水害から守ります。ジッパー付きの袋がおすすめです。
家族で共有:
記録を家族で共有し、避難時に1部ずつ持つようにします。コピーを取っておくといいです。
デジタル保存:
スマホにデータを保存し、クラウドにアップロードしておくと、どこからでもアクセスできます。

災害が起きた後の簡単モニタリング
3.1 基本健康チェック
限られた状況での健康観察が求められます。以下を行いましょう。
体温を測る:
肛門で測り38℃以下または40℃以上は異常のサインです。
水の摂取量:
1日あたりの飲み水の量を観察します。減っていたら脱水の可能性があるので注意が必要です。
行動を観る:
活動量や食欲を記録します。元気がないのはストレスのサインなので、よく様子を見ましょう。
3.2 簡単な診断ツールを使う
手元でできるツールを活用しましょう。
脈拍を確認:
1分間の心拍数を測ります(犬: 60~140回、猫: 120~140回)。
粘膜を見る:
歯茎の色をチェックします。淡い色は脱水の可能性があるので、唇や舌も一緒に観察してみましょう。
手書き記録:
紙とペンで日時と一緒に症状を書き留めます。懐中電灯で夜でも見えるように準備しておくと便利です。
3.3 ストレス管理と一緒に
健康記録にペットの行動も記録しておきましょう。
行動のパターン:
隠れる、震えるなどの変化をメモします。どこで隠れるかも記録すると傾向がわかります。
休む時間:
睡眠時間や休息の回数を記録します。長時間寝すぎるのも、逆に寝ないのも注意が必要です。
安心を与える:
馴染みの毛布やおもちゃを用意して、ストレスを減らします。落ち着く場所を決めてあげると効果的です。

地域ごとの健康記録の工夫
4.1 東日本(地震対策)
地震後は埃や振動でペットのストレスが増えるので、呼吸音や咳の回数を特に記録するようにします。
4.2 西日本(台風・洪水対策)
洪水後は湿気で皮膚トラブルが出やすいので、足の状態や湿疹を写真に収めます。毎日チェックして、赤みやかゆみをメモしましょう。
4.3 北海道(豪雪対策)
豪雪後は低体温のリスクがあるので、体温と震えの頻度を詳しく記録します。暖房を使う環境や部屋の温度もメモしておくとあとで役立ちます。
健康記録を作るコツ
5.1 手作り健康チャート
お得な方法として、A4用紙とマーカーで簡単な健康チャートを作ってみましょう。体重や体温をグラフにすると異常がわかりやすいですし材料費は100円ほどで済みます。毎月更新できるので経済的で家族で使うのにもおすすめです。
5.2 リサイクルノートの活用
使い終わったノートやカレンダーの裏を再利用して、健康記録用にしてみましょう。表紙に「健康記録」と書いて目印にするとわかりやすいです。

注意点とリスクを減らす方法
6.1 観察の正確さに気をつける
素人判断だけに頼らず、異常があれば獣医師に相談します。記録は事実をそのまま書いて、推測は避けるようにしましょう。
6.2 プライバシーを守る
健康記録は家族以外に見られないように鍵付きの箱やパスワードで管理するとよいでしょう。紛失や盗難に気をつけて、1部を安全な場所に
保管しましょう。
6.3 モニタリングを続ける
停電時は懐中電灯や手動時計などを一緒に使い記録を中断しないようにします。電池を予備で2~3個用意しておくと安心です。
自宅でのさらなるモニタリングアイデア
音声メモを取る:
症状の詳細をスマホで録音し、後で聞き直して記録します。声でメモすると、手がふさがらず便利です。
家族で役割分担:
健康チェックを家族で役割を分けて個々の負担を減らします。たとえば、誰かが体重測定を、誰かが体温測定を担当するなど。
簡易キットを用意:
体温計とメモを1セットにまとめ、持ち運びしやすくします。小さな袋に入れてから避難バッグに入れるようにしましょう。
行動日記:
ペットの遊び方や気分を毎日メモして、ストレス状態を把握します。楽しそうな場面や元気な姿も記録に残しておきましょう。
季節での調整:
夏は熱中症、冬は低体温に注意し、体温を毎日測る習慣をつけます。気温を一緒にメモすると傾向がわかります。

早わかり表:災害時の健康記録
| 項目 | 詳細 | 災害時のポイント |
|---|---|---|
| 基本情報 | 名前、年齢、過去の病気、普段の状態 | 緊急時の判断材料として準備 |
| モニタリングツール | 体温計、はかり、ノートやアプリ | 簡単で正確な観察をサポート |
| 定期観察 | 週1回チェック、月1回写真、異常時記録 | 継続的な健康追跡 |
| 災害中モニタリング | 体温、水分摂取、行動観察 | 限られた状況での健康管理 |
| 災害後 | データ更新、長期モニタリング、健康回復追跡 | 回復過程の記録と継続性確保 |
まとめ:健康記録を習慣化しペットを守っていこう
ペットの健康記録は本当に重要です。常にモニタリングする習慣があれば異常を早く見つけられ、災害中でも焦る事なく対応することが出来ます。愛するペットとの安全な毎日を守る為に、今日から一歩踏み出してみましょう!