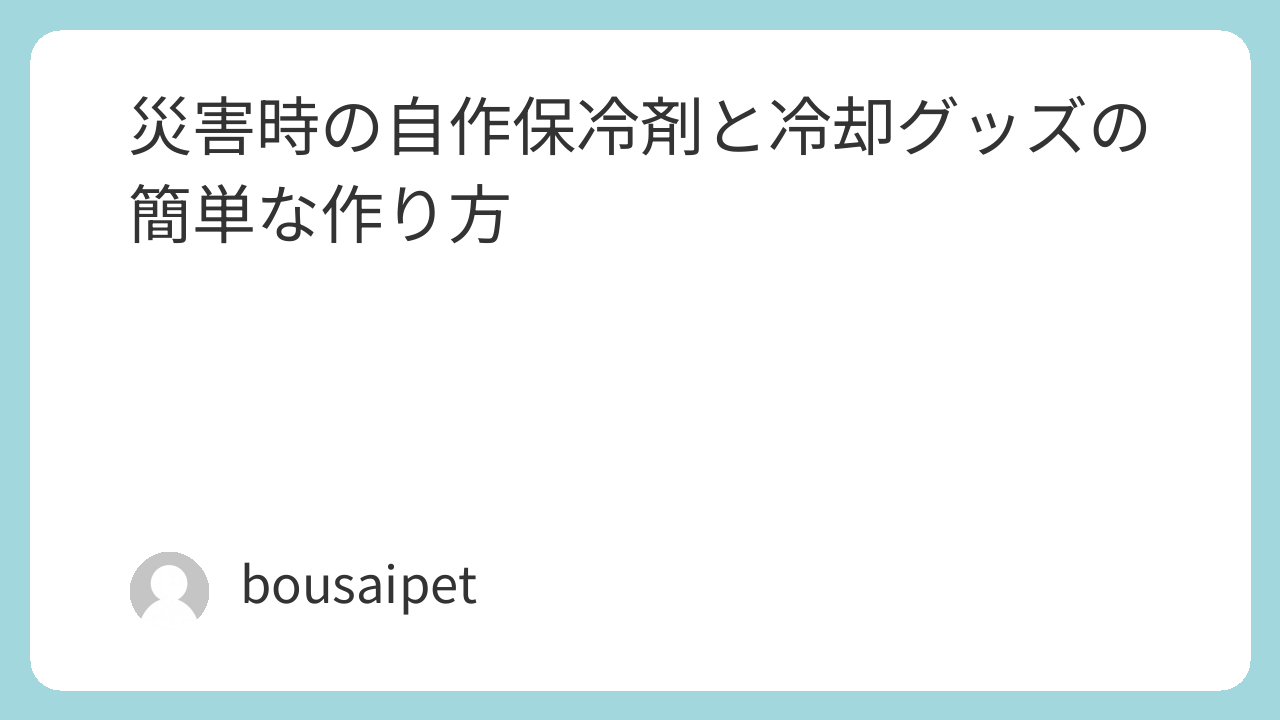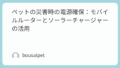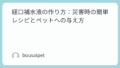猛暑時に停電が起こった場合、ペットだけでなく人も熱中症の危険にさらされます。ネット上では、「停電でエアコンが止まり、犬がぐったりして焦った」「暑さで自分もペットもバテてしまった」といった声が非常に多く、冷却対策への関心が高まっています。
この記事では、ペットと人両方に使える自作保冷剤や簡易冷却グッズの作り方を詳しくご紹介していきます。
災害時になぜペットと人に冷却対策は必要なのか
災害時には、ペットも人も快適で安全な環境を保つことが大切になります。夏場の停電でエアコンが使えなくなると、室内の温度が急上昇し、熱中症のリスクが高まります。たとえば、犬や猫は体温調節が難しく、気温が30℃を超えると危険な状態になりやすいです。ハムスターや鳥、魚などの小動物も高温に弱く、ケージや水槽の温度管理が欠かせません。人間にとっても、猛暑は体力を奪い、集中力を下げる原因になります。
ネット上の声では、「停電で水槽の温度が上がり、魚が弱ってしまった」「暑さで自分もペットも寝られなかった」といった投稿が目立ち、冷却対策の重要性がわかります。そこで、保冷剤や冷却グッズを自作する事が出来れば、電気もお金もかけずに体調を維持する事が出来るんです。もちろん市販品でもいいのですが、災害時には入手が難しい状況になりやすいです。
自作なら低コストで準備でき、ペットと人両方に使えるので、どんなご家庭でも重宝すると思います。ペットを飼っていない方でも、猛暑時の避難所や車中泊で活用できるため、幅広いニーズに対応する事ができます。
ペットも人にも使える自作保冷剤の作り方
2.1 吸水シートを使った保冷剤
吸水シートを使った保冷剤は、簡単で安全、ペットと人両方に使える方法としてネットでも話題になっています。低コストで作れるので、災害に備えてたくさん用意できます。以下に手順をご紹介しますね。
材料を準備:
吸水シート(ペットシーツや赤ちゃん用シート)、ジップ付きの保存袋(中サイズ)、水。
シートを折る:
吸水シートを保存袋に入る大きさに折り、袋に入れる。
水を加える:
シートが吸収できる量の水(約200~300ml)を注ぎ、全体がしっとりするまで浸す。
冷凍する:
袋の空気を抜いて密封し、冷凍庫で4~6時間凍らせる。
完成:
薄くて広い面積で冷える保冷剤の完成です。ペットの寝床やキャリーバッグに敷いたり、
人の首や額にタオルで包んで当てたりします。

ポイント:
吸水シートは柔らかく、凍っても硬くなりすぎないので、ペットの体や人の肌に優しくフィットします。解凍後は乾燥させて再利用も出来ますよ。
お得な工夫:保冷剤を長持ちさせる方法
保冷剤をタオルや布で包んで使うと、冷たさが長く続き、結露も防げます。ネットでは、「タオルで包むと3時間近く涼しかった」「ペットも人も快適だった」との声があります。人間なら首筋や脇の下、ペットなら背中やお腹に当てると効果的です!
2.2 尿素で作る瞬間冷却パック
冷凍庫が使えない状況では、尿素を使った瞬間冷却パックが便利です。ペットと人両方に使え、災害時の緊急対応にも役立ちます。以下に作り方をご説明します。
材料を準備:
尿素(園芸店やホームセンターで購入可能、約200g)、水(約100ml)、厚手のジップ付き保存袋2枚。
袋を分ける:
尿素を1枚の袋に入れ、別の袋に水を入れる。
二重構造にする:
水の袋を尿素の袋の中に入れ、両方をしっかり密封する。
使用時:
袋を軽く叩いて水の袋を破り、尿素と水を混ぜる。吸熱反応で急速に冷える。
完成:
タオルで包んで、ペットの体や人の額、首に当てる。
注意:
尿素はペットや人が直接触れないよう、タオルで保護しておきましょう。使用後は適切に廃棄しましょう。
お得な工夫:瞬間冷却パックの備蓄術
尿素を小分けにして密閉容器に保存しておくと、必要なときにすぐ作れます。災害時に慌てないよう、試作用に少量を使って作り方を練習しておくと安心です。ネットでは、「小分けにしたら準備が楽だった」という声が聞かれます。

簡易冷却グッズの自作アイデア
3.1 濡れタオルで作る冷却シート
市販の冷却マットがなくても、身近な素材で代用品が作れます。この方法はペットのケージや人の休憩スペースでも使えます。
材料:
吸水性の高いタオル(マイクロファイバー推奨)、水、ビニールシート。
作り方:
タオルを水で濡らし、軽く絞って湿らせた状態にする。ビニールシートの上にタオルを広げ、ペットの寝床や人の座る場所に敷く。冷蔵庫があれば、濡らしたタオルを冷やして使うとさらに効果的です。
活用シーン:
ペットのキャリーバッグや避難所のスペース、人の仮眠スペースで使用します。
ポイント:
ビニールシートは水漏れを防ぎ、衛生的に使えます。タオルはこまめに洗い、清潔に保ちましょう。
3.2 凍らせたボトルで冷却する
プラスチックボトルを使った冷却グッズは、シンプルで効果的です。ペットと人両方に使えます。
材料:
500mlまたは250mlのプラスチックボトル、水。
作り方:
ボトルに水を8割程度入れ、冷凍庫で凍らせる。
凍ったボトルをタオルで包み、ペットのケージや人の近くに置く。
小型ペット(ハムスターや鳥)や子どもには、250mlの小さいボトルが安全です。
活用シーン:
水槽やケージの温度管理、人の首や足元の冷却に最適です。
ネットでは、「凍らせたボトルをタオルで包んだら、ペットが涼しそうに寝ていた」「自分も車中泊で使えて助かった」といった声が多く、自作冷却グッズとしても需要が高いことがわかります。

災害前に準備しておきたいこと
ネット上の声や専門家のアドバイス情報を基に、ペットと人に必要な準備をまとめてみました。
4.1 防災グッズの準備
食料と水:
ペットと人それぞれに7日分以上の食料と水を用意する。ペットは長期保存可能なフードがいいです。
医療用品:
ペットの薬や傷の手当てキット、人の常備薬。獣医師やかかりつけ医の連絡先をメモしておくといいです。
キャリーバッグや避難用品:
ペットを安全に運べる丈夫なバッグ、人が使える折り畳みマットを用意します。

冷却・保温グッズ:
自作保冷剤や濡れタオル、冬用のブランケットを準備します。
身元証明:
ペットには迷子札やマイクロチップ、人のIDカードを常備します。
4.2 避難計画を立てる
避難所の確認:
ペット同伴可能な避難所や、人が利用する避難所のルールを自治体のサイトで確認します。
避難ルートの確認:
洪水や土砂災害を避ける安全なルートを家族で共有します。
近隣との連携:
ペットの世話や人の安否確認を頼める近隣住民と連絡網を作っておきます。
4.3 冷却対策の準備
保冷剤の材料:
吸水シートや尿素を常備し、いつでも作れるようにしておきます。
ポータブル電源の準備:
500Wh以上の容量で、扇風機や小型冷却機器を動かせるモデルを選びます。

水の確保:
断水に備え、ペットと人の飲料水を多めにストックします。浴槽に水を溜める習慣も有効です。
ネットでは、「停電で水が足りず困った」「冷却グッズがなく、ペットも自分も辛かった」
といった声が多く、事前準備の重要性が強調されています。
災害リスクと冷却対策のポイント
5.1 地震
気象庁によると、首都直下地震や南海トラフ地震のリスク増大が指摘されています。停電や断水が長引く可能性があり、冷却対策が重要になってきています。
耐震対策:
ペットのケージや水槽、人の家具を固定し、落下物を防ぎます。飛散防止フィルムも活用するといいです。
冷却グッズの準備:
自作保冷剤や凍らせたボトルを冷凍庫に常備しておきます。
5.2 台風
台風シーズンは9月~10月にピークを迎えます。過去の台風では、停電や洪水がペットと人に大きく影響を与えました。
高台への避難:
洪水リスクの低い場所への移動ルートを確認します。
防水対策:
保冷剤や冷却グッズを防水バッグに保管しておきます。
5.3 猛暑
今後の夏も引き続き猛暑が予想され、ペットと人の熱中症リスクが高まります。ネットでは、「エアコンが止まり、ペットが苦しそうだった」「自分も暑さで体調を崩した」といった声が多数見受けられました。
自作冷却グッズ:
吸水シート保冷剤やボトル冷却を複数用意しておきます。
水分補給:
ペット用の自動給水器、人の水筒を複数常備しておきます。

ペットと人の災害時冷却対策:早わかり表
ペットと人に使える冷却対策のアイテムとポイントを表にまとめてみました。準備の参考にしてみましょう。
| アイテム | 必要な機能 | 活用シーン | ポイント |
|---|---|---|---|
| 吸水シート保冷剤 | 吸水性の高いシート、ジップ付き保存袋 | ペットの寝床や人の首・額の冷却 | タオルで包んで長持ちさせる |
| 瞬間冷却パック | 尿素と水、厚手の保存袋 | 冷凍庫がない環境での即時冷却 | 尿素を小分けでストック |
| 濡れタオル冷却シート | 吸水タオル、ビニールシート | ペットのケージや人の休憩スペース | タオルを清潔に保つ |
| ボトル冷却 | 500mlまたは250mlボトル | 水槽や人の足元の冷却 | タオルで包んで安全に |
| ポータブル電源 | 500Wh以上、1時間以内のフル充電 | 扇風機や冷却機器の稼働 | 消費電力を事前に確認 |
まとめ:ペットと人を守る冷却対策を今からはじめよう
地震や台風、猛暑といった災害は、いつ起こるかわかりません。年々規模も大きくなって来ています。ペットも人も快適に過ごすためには、自作保冷剤や冷却グッズの準備が欠かせなくなって来ています。早速、以下の項目を参考に、準備を始めてみましょう!
吸水シート保冷剤を用意:簡単で低コストな冷却グッズを常備しておく。
瞬間冷却パックをストック:冷凍庫がない環境でも使える材料を準備しておく。
ポータブル電源を導入:扇風機や冷却機器を動かせるモデルの電源購入を検討しておく。
防災グッズをチェック:食料、水、医療キットを定期的に確認しておく。