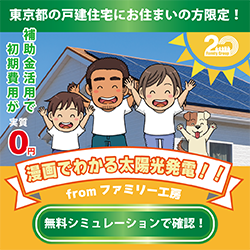災害による停電、断水、道路の寸断といったインフラへの影響は、家族だけでなく、ペットの生活にも大きな影響を与えますよね。台風15号では、千葉県で長期間の停電や断水が続き、ペットの世話に困った飼い主さんの声がSNSでたくさん上がっていました。停電でペットの水槽が動かなくて焦った」「道路が通れずペットフードが買えなかった」といった投稿を見ると、インフラ被害への不安が強いことがわかります。この記事では、台風や豪雨によるインフラ被害の現状と、ペットと家族を守るための具体的な準備や対策をわかりやすくお話していきます。
インフラ被害の実態とリスク
日本は台風や豪雨が頻繁に起こる国ですが、特に最近は、気候変動の影響で災害の規模が
大きくなってきています。台風15号では、千葉県で約64万戸が停電し、復旧に2週間以上かかった地域もありました。断水も約14万戸に及び、給水車を待つ行列ができた中、
ペットの飲み水や衛生管理に苦労したという声がネットで多く聞かれました。台風10号でも、九州や東海で大雨による道路の寸断が起き、物資の供給が遅れてペットフードが足りなくなった地域もあったといいます。インフラ被害の主なリスクは次の3つになります。
停電:
電気が止まると、エアコンや照明、冷蔵庫が使えなくなり、家族だけでなく、ペットのストレスや健康リスクが高まります。夏の暑さや冬の寒さは、ペットにとって命に関わる問題になります。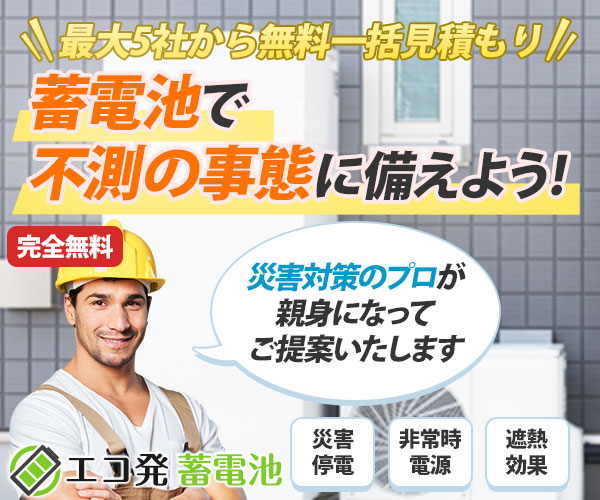
断水:
水道が止まると、飲み水や衛生管理が難しくなり、ペットの健康にも影響が出てきます。
道路の寸断:
道路が通れなくなると、避難や物資の調達が難しく、孤立するリスクが出てきます。ペットを連れて移動するのさえ大変になります。
なぜインフラ被害が深刻化してるのか
気候変動による災害の拡大:
気象庁によると、地球温暖化で海の表面の温度が上がり、台風や豪雨の規模が大きくなってるんだとか。これにより、電柱が倒れたり、変電所が水没したり、道路が流されたりするケースが増えてきています。2019年の台風19号では、関東から東北で約52万戸が停電し、インフラの弱さが目に見えてわかりました。家族とペットを守るには、こんな大きな災害を想定した準備が必要になってきます。
インフラの老朽化:
日本の電力や水道の設備は、1960年代から70年代に作られたものが多く、かなり古くなってきてます。台風15号のとき、強風で電柱が倒れたり、送電線が切れたりした背景には、設備の老朽化もあると指摘されてます。
都市部と地方の違い:
都市部は人が多い分、インフラの復旧が優先されがちです。でも、地方だと道路や電力の復旧が遅れることが多いんです。ネットでは、「地方に住んでると停電が長引いて、ペットフードを買いに行けなかった」っていう声も聞きます。特にペットを飼ってる家庭では、孤立に備えた準備が大事になってきます。

インフラ被害に備える準備と行動
インフラ被害に備えるには、停電、断水、道路の寸断を想定した準備が必要になってきます。ペットを飼ってるご家庭では、ペットの安全と快適さを守るための特別な準備も必要になります。以下に、具体的な準備物と行動をまとめました。
1.準備しておきたい物
停電対策
ポータブル電源:
スマホの充電やペットのケージの冷却ファンに使える小型の電源。容量1000Wh以上のものがおすすめです。
LEDランタン・懐中電灯:
停電時の明かりにします。ペットのケージ周りを照らすのに、電池式が便利です。
ペット用冷却グッズ:
夏の停電に備えて、冷却マットや保冷剤を用意します。犬や猫の熱中症を防ぐのに必須です。
予備の電池:
ラジオや懐中電灯用に、単3・単4電池を多めにストックしておきます。
断水対策
飲料水:
1人1日3リットル、ペット1匹(中型犬や猫)1日1リットルを目安に、7日分を準備します。
ペット用ボトル:
ペットが普段飲む水をストックして、体調を崩さないようにします。専用の給水ボトルも用意しておきましょう。
簡易トイレ:
人間用とペット用の簡易トイレキットを用意します。ペット用の吸収シートも多めに準備しましょう。

ウェットティッシュ・除菌スプレー:
断水時の衛生管理に使います。ペットの足やケージを清潔に保つのにも役立ちます。
道路の寸断・孤立対策
非常食:
人間用(レトルトやインスタント)とペット用(ドライフード、ウェットフード)を7日分以上用意します。
折りたたみケージ:
避難時にペットを安全に運ぶ時に使います。軽くて持ち運びやすいものがいいですね。
リード・ハーネス:
道路が寸断されても、ペットを安全に移動させる丈夫なリードやハーネスがよいです。
ハザードマップ:
自宅周辺の避難ルートやペット同伴OKの避難所を確認しておきます。自治体のサイトやNHKの災害情報マップを活用するとよいでしょう。
その他の必要な物
ペット用防寒グッズ:
冬の停電に備えて、ペット用の毛布や暖かいパッドを用意します。
ペットの情報書類:
ワクチン証明書や健康状態を記載した書類を防水ケースに入れておきます。
救急キット:
人間用とペット用の絆創膏、消毒液、常備薬を用意します。

2.事前にしておきたい行動
ハザードマップと避難所の確認:
自治体のハザードマップで、洪水や土砂災害の危険をチェックしておきます。ペット同伴可能な避難所を事前に確認し、連絡先をメモしておきます。
家の点検と補強:
屋根や外壁の補修、排水溝の掃除で浸水のリスクを減らしておきます。ペットのケージを高い場所に置き、落下物から守れるようにしておきます。家具を固定したり、窓に飛散防止フィルムを貼ったりして、停電や地震時の安全を確保しておきましょう。
情報収集の準備:
気象庁の「防災気象情報」やNHKの速報をチェックします。スマホに「NHK World」アプリを入れて、緊急情報を受け取れるようにするとよいでしょう。ポータブルラジオを用意して、停電時でも情報がわかるようにしましょう。
ペットとの避難訓練:
家族とペットで避難ルートを確認しておきます。ペットをケージに入れる練習や、リードでの移動を慣らしておくとよいでしょう。夜間や停電時の訓練をして、ペットが落ち着いて行動できるようにしましょう。
私が経験したインフラ被害の実話:学んだこと
2020年の台風12号のとき、私の住む地域は大雨で停電と断水に見舞われました。夜中に突然電気が止まり、愛猫が暗闇でそわそわし始めたのが印象的でした。いつも使ってる自動給水器が動かず、ペットの水を確保するのに焦りましたね。近所のスーパーも道路の冠水で閉まってて、ペットフードの買い足しができない状況でした。幸い、事前に用意していた水とフードでしのげましたが、停電でエアコンが使えず、猫が暑そうにしてるのが心配でした。この経験で、ペットの防災準備の大切さをとても痛感しました。特に、停電時のペットの体温管理や、断水時の水の確保が大事だと気づきました。今は、ポータブル電源やペット用の冷却マットを常備し、フードや水を多めにストックしてます。ペット同伴可能な避難所の場所も確認済みで、猫の健康情報をまとめた書類も用意しています。

災害時のインフラ被害への対処法
停電時の対処
電力の優先利用:
ポータブル電源でスマホやペットの冷却ファンを動かします。電力は大事に使い、バッテリーを長持ちさせましょう。
ペットのストレス対策:
暗闇でペットが不安にならないよう、LEDランタンでケージ周りを明るくします。いつもの毛布やおもちゃを近くに置いて安心感を与えてあげましょう。
温度管理:
夏は冷却マットや保冷剤、冬はペット用毛布で体温を調整します。ペットの様子をこまめにチェックしましょう。
断水時の対処
水の優先順位:
人間とペットの飲み水を最優先します。残りは衛生管理やトイレに使うとよいでしょう。
ペットの衛生:
ウェットティッシュでペットの体を拭き、ケージを清潔にします。ペット用の吸収シートはこまめに交換しましょう。
給水車の活用:
自治体の給水車情報をチェックしておきます。いざというときはペット用の容器を持参して水を確保します。
道路の寸断・孤立時の対処
ルート確認:
ハザードマップで複数の避難ルートをチェックしておきます。ペットを連れて歩ける道を選ぶとよいでしょう。
ペットの安全:
避難時はペットをケージやリードでしっかり確保しておきます。逃げないよう、首輪に連絡先のタグを付けておくとよいです。

地域の連携:
近隣住民と連絡網を作り、ペットフードの共有や助け合いが出来るとよいです。
早わかり表:インフラ被害とペット防災への備え
| 項目 | 準備物・行動 |
|---|---|
| 停電対策 | ポータブル電源、LEDランタン、ペット用冷却マット・防寒グッズ、予備電池 |
| 断水対策 | 飲料水(人間7日分、ペット1匹1日1L)、ペット用ボトル、簡易トイレ、ウェットティッシュ |
| 道路の寸断・孤立対策 | 非常食(人間・ペット7日分)、折りたたみケージ、リード、ハザードマップ |
| 事前の行動 | ハザードマップ確認、家の補強、情報収集、ペットとの避難訓練 |
| 災害時の行動 | 電力・水の優先利用、ペットのストレス管理、ルート確認、地域連携 |
国や自治体の取り組みと私たちの役割
政府や自治体は、インフラ被害を減らすために動いているようです。内閣府は災害救助法を適用し、停電や断水の復旧支援を強化していますし、気象庁は高精度レーダーのRAINや早期警報で、災害時の予測性能を向上させているようです。2019年の台風15号の教訓から、電力会社は電柱の補強や地下送電線の導入を進めて、復旧時間を短くしようとしています。でも、地方だと復旧が遅れることも多く、個人や地域での備えが大事になってきます。特にペットを飼ってる家庭では、ペット同伴OKの避難所を事前にチェックしたり、近所の飼い主さんと助け合いのネットワークを作っておくことが、今後の有事の際に役立つのは間違いないと思っています。

まとめ:これからの展望と私たちにできること
気象庁は、今後も台風や豪雨の規模が更に大きくなる可能性があると予測しています。インフラの強化にはとても時間がかかるので、個人でできる準備がますます大事になります。ペットを守るために、まずはこんな行動が役立ちます。
環境への配慮:
節電やリサイクル、公共交通の利用など、少しでも気候変動を抑える小さな努力をする。
地域の協力:
ペット飼い主同士で防災情報を共有し、災害時にの助け合えるようにする。
防災教育:
家族や子どもにも、ペットとの避難方法やインフラ被害への対処法を教えておく。