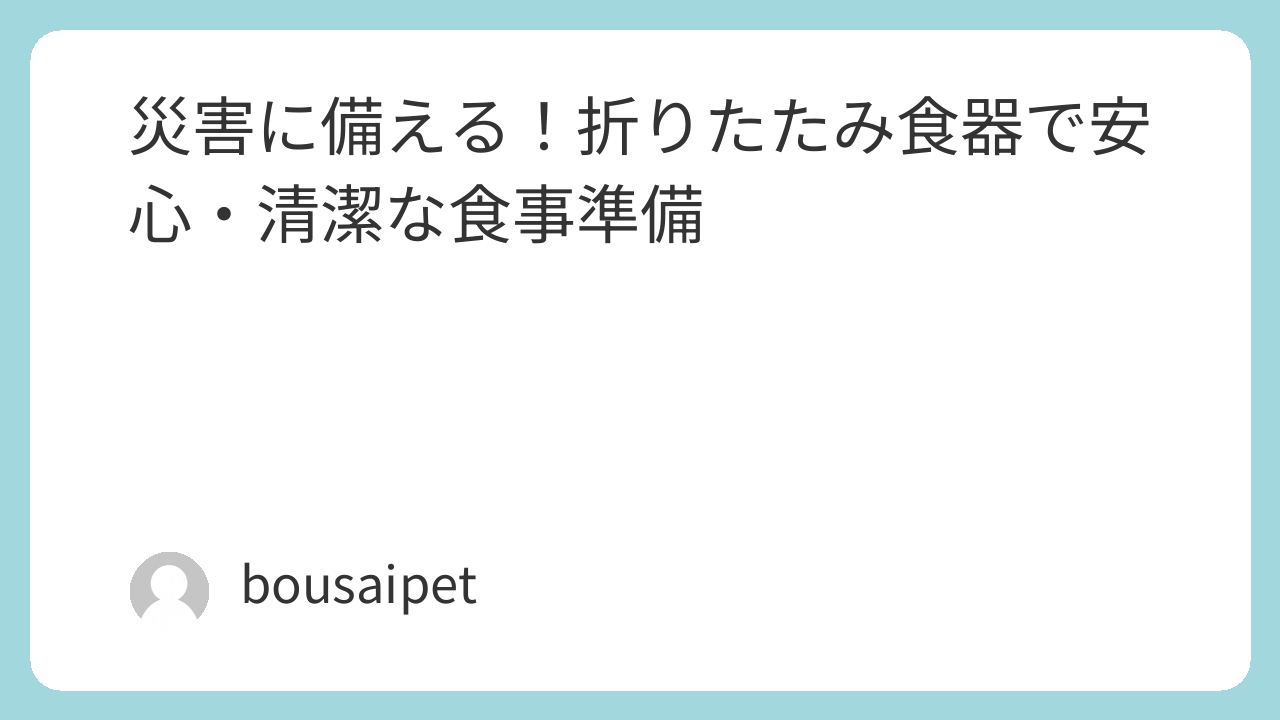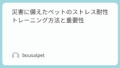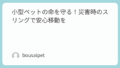ペットと一緒に安全に避難する際、食器の準備はとっても大事です。そんな時折りたたみ食器があれば、避難バッグにスッキリ収まり、清潔に使えるので、災害時であってもペットの健康を守っていけます。
この記事では、犬、猫、鳥、小動物に合わせた折りたたみ食器の選び方や使い方をわかりやすくご紹介していきます。
折りたたみ食器の大切さ
災害時にペットが落ち着いてご飯や水を摂れる環境を整えることは、ペットの健康を保ち、ストレスを減らすためには欠かせません。折りたたみ食器は、限られたスペースで
使いやすく、清潔な食事環境をサポートする頼もしいアイテムになります。
1-1. なぜ折りたたみ食器が必要なの?
災害時には、避難所や車の中で過ごすことが多くなるので、荷物はできるだけコンパクト
にしたいですよね。普通の食器は大きくてかさばるけど、折りたたみ食器なら小さく畳めて持ち運びも簡単です。たとえば、2016年の九州での大地震では、避難所でペットの食事を管理する際、大きな食器が邪魔になり、清潔さを保つのが大変だったケースがあったそうです。折りたたみ食器は、シリコンや布でできていて、軽くてポケットにも入るサイズもあります。洗いやすくて乾きも早いから、水が少ないときでも清潔に使えます。
1-2. 折りたたみ食器がないとどうなる?
折りたたみ食器がないと、災害時にペットの食事が乱れがちになります。2020年の
九州豪雨では、避難所で適切な食器がなく、ペットが床で直接ご飯を食べたりして、
衛生面で問題が起きたことがありました。リスクとしては次の通りです。
(1)大きな食器で避難バッグがパンパンになる。
(2)汚れた環境での食事でペットが病気にかかる。
(3)食事の時間が不安定になり、ペットの体調が悪くなる。
*紙皿や適当な容器で代用すると、汚れが落ちにくかったり、ペットがご飯を嫌がったりすることもあります。折りたたみ食器を用意しておけば、こうしたトラブルをグッと減らせます。
1-3. ペットの種類の違いによる食器のニーズ
ペットの種類によって、食器に求めるものが違います。犬は水やご飯をたっぷり入れる深めのボウルがいいし、猫は少しずつ食べるから浅い皿がぴったりです。鳥は小さくて安定した容器、小動物(ハムスター、ウサギ、モルモット)はこぼれにくい形のものが必要です。たとえば、モルモットは動き回るので、倒れにくい食器がよいでしょう。折りたたみ食器は、ペットの種類に合わせたサイズや形を選べるので、災害時の食事でも最適です。
1-4. 折りたたみ食器のいいところ
折りたたみ食器は、スペースを取らず、持ち運びが楽で、洗いやすいのが魅力です。避難所のような狭い場所でも使いやすく、乾きやすい素材なら水が少ないときでも清潔さを保てます。たとえば、シリコン製のボウルは畳めば薄くなり、熱湯で消毒もできます。
1-5. 災害時の食事環境の重要性
ペットは環境が変わると食欲が落ちやすいです。避難所や車中泊では、慣れない場所でストレスを感じ、食事量が減ることがあります。折りたたみ食器なら、普段と同じような食事環境を再現でき、ペットの安心感にもつながります。たとえば、猫がいつもと同じボウルで食べると、ストレスが軽減されることがあります。

折りたたみ食器の選び方と種類
災害時に役立つ折りたたみ食器を選ぶには、素材、サイズ、使いやすさがポイントになります。ペットの種類ごとに、ぴったりの食器の選び方をご紹介します。
2-1. 犬のための折りたたみ食器
犬は水やご飯をしっかり食べるので、大きめで安定感のある食器がいいですね。

素材:
シリコンがおすすめです。軽くて畳めるし、洗いやすいです。熱にも強いから温かいご飯にも使えます。
サイズ:
中型犬なら500ml、大型犬なら1リットル以上がよいでしょう。
特徴:
滑り止めがついた底や、バッグに引っ掛けられるクリップ付きが便利です。また、深さ5cm以上のボウルならこぼれにくいです。
2-2. 猫のための折りたたみ食器
猫は少しずつ食べるので、浅くて小さな食器が向いています。
素材:
ナイロンやシリコンがよいです。乾きが早くて、水が少ないときでも清潔さを保てます。
サイズ:
200~300mlの小さいボウルがよいです。畳むとポケットに入るサイズがおすすめです。
特徴:
縁が低くて食べやすい形ものを選びます。防水の布製も軽くて使いやすいです。
2-3. 鳥のための折りたたみ食器
鳥は小さな容器で十分ですが安定感が大事です。
素材:
軽いプラスチックやシリコンがよいです。ケージに固定できるものがおすすめです。
サイズ:
50~100ml。畳むと手のひらサイズのものを選びましょう。
特徴:
クリップや吸盤で固定できるもの。こぼれにくいデザインを選びましょう。
2-4. 小動物(ハムスター、ウサギ、モルモット)のための折りたたみ食器
小動物にはご飯がこぼれない食器が必要です。
素材:
シリコンや布製で軽くて洗いやすいものがよいです。
サイズ:
50~150ml。畳むとコンパクトになるものを選びます。
特徴:
底が重いデザインや、ケージに引っ掛けられるフック付きが便利です。モルモットは動きが活発なので、倒れにくい形状のものがおすすめです。

折りたたみ食器の使い方と清潔に保つコツ
折りたたみ食器を上手に使うには、正しい使い方と清潔さが大切です。災害時の限られた
環境でも衛生的に使える方法をご紹介します。
3-1. 使い方のポイント
準備:
食器を広げて、平らな場所に置きます。シリコン製なら底を押して形を整える事ができます。
ご飯や水を入れる:
ペットの食事量に合わせて適量を入れます。犬は1日2回、猫は3~4回、鳥や小動物は1~2回に分けます。
収納:
使った後は畳んで防水バッグにしまいます。クリップ付きならバッグの外に引っ掛ける事もできます。
3-2. 清潔に保つ
コツ洗う:
少量の水と洗剤で洗います。水がないときは除菌シートで拭くとよいです。
乾かす:
乾きやすい素材を選び、風通しのいい場所で乾かします。シリコンなら5分で乾きますよ。
消毒:
週1回、熱湯(80℃以上)で5分消毒します。プラスチックは熱に強いか確認しましょう。
3-3. 避難所での注意
避難所では、ほかのペットや人とのスペースを考えて使いましょう。食器は使ったらすぐ洗って、専用バッグにしまいます。ほかのペットの匂いが付かないように、個別に管理しましょう。
3-4. 長く使うためのメンテナンス
折りたたみ食器は丈夫ですが、定期的にチェックしましょう。シリコンのひび割れや布の
ほつれを見つけたら1年ごとに買い替えを考えましょう。
3-5. 断水時の工夫
水が少ない場合、ペットボトルのキャップ1杯分の水で洗います。濡れタオルで拭いてから除菌シートを使うと、節水しながら清潔に使えます。

折りたたみ食器を災害準備に取り入れる
折りたたみ食器を災害時のペット対策にうまく組み込む方法をご紹介します。
4-1. 避難バッグへの収納
折りたたみ食器は避難バッグの外ポケットやクリップで固定します。1バッグに2~3個
(ご飯用、水用)入れておきましょう。シリコン製なら2個で100g以下と軽いです。
4-2. ご飯のスケジュール計画
災害時にペットのご飯スケジュールを決めます。犬は朝と夕方、猫は1日3回、小動物は夜が中心になります。食器の数をスケジュールに合わせましょう。

4-3. ほかの防災グッズとの組み合わせ
折りたたみ食器は、ご飯のストックや水ボトルと一緒に準備します。
4-4. ペットの食事環境の工夫
避難所では、静かな場所で食事を与えます。毛布やタオルで仕切りを作ると、ペットが落ち着いて食べてくれます。

折りたたみ食器を使ったトレーニング
折りたたみ食器に慣れるトレーニングをしましょう。
5-1. 食器に慣らす
毎日5分、折りたたみ食器でご飯や水をあげてみます。犬や猫は1週間で慣れます。小動物は2週間、鳥は3週間かかることもあります。
5-2. 模擬避難での練習
定期的に避難バッグから食器を出して、家の外でご飯をあげてみます。15分くらいで、ペットが落ち着いて食べるかチェックしてみましょう。
5-3. いろんな場所で練習
食器を庭や玄関で使って、場所が変わっても慣れるようにします。猫や鳥に特に効果的です。
5-4. 子供に清潔習慣を身につける
子供と一緒に、食器の洗い方や収納を練習します。
5-5. おやつを使って慣らす
ペットが食器を嫌がる場合、おやつを少し入れて慣らします。
5-6. ペットのストレスサインをチェック
食器を使うとき、ペットの様子を観察します。食器を嫌がって震えたり、猫が隠れたりしたら、時間を短くして慣らしましょう。

早わかり表:ペットごとの折りたたみ食器の選び方
| ペット | 素材 | サイズ | 特徴 | 清潔のコツ |
|---|---|---|---|---|
| 犬 | シリコン | 500~1000ml | 滑り止め、クリップ | 熱湯消毒、速乾 |
| 猫 | ナイロン、シリコン | 200~300ml | 浅い縁、防水 | 除菌シート、乾燥 |
| 鳥 | プラスチック | 50~100ml | 固定クリップ | 煮沸、速乾 |
| 小動物 | シリコン、布 | 50~150ml | 重い底、フック | 洗剤洗い、乾燥 |
まとめ:折りたたみ食器を準備して災害時に備える
災害時にペットの食事環境を整えるには、折りたたみ食器が大活躍します。さっそく以下のステップから始めていってみましょう。
ペットに合う食器を選ぶ:
素材やサイズをチェックする。
清潔さを保つ:
食器の洗い方や消毒の習慣を身につける。
避難バッグに入れておく:
非常用のご飯や水と一緒に折りたたみ食器も必要分入れておく。