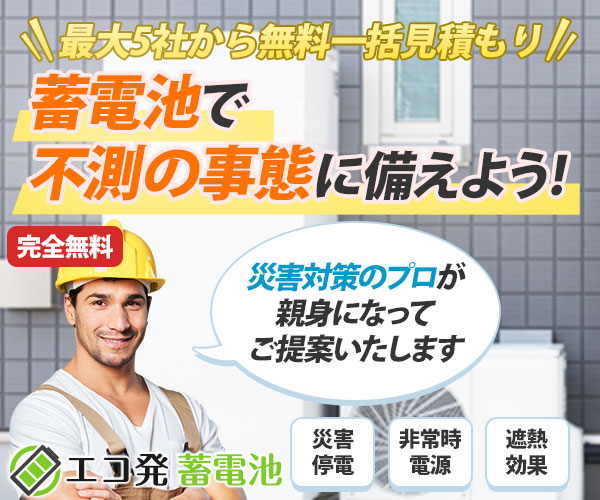最近、日本では台風や豪雨による災害がどんどん深刻になってきています。2024年の台風5号や台風10号のような「のんびり進む台風」や、線状降水帯による大雨が、洪水や土砂災害を引き起こして、みんなの生活に影響を与えています。ネットでも「こんな大雨、初めてだよ」っていう不安の声がたくさん聞こえてきて、防災への関心がぐっと高まってるのがわかります。
この記事では、台風や豪雨の被害のリアルな状況、原因、そして今すぐできる準備や行動をわかりやすくお話していきます。
台風や豪雨の被害のリアルな状況
最近は、地球温暖化の影響で大雨の回数や強さが徐々に増えているんだそうです。1901年以降、1日の降水量が200mmを超える日がぐっと増えてるってデータもあるんです。2024年の台風10号は特に話題になりました。西日本から東日本の太平洋側にすごい大雨を降らせました。一部の地域では、総雨量が900mmを超えて、九州や東海では48時間で400mm以上の雨が降り、過去最高の降水量を記録したところもあって、川が溢れたり、土砂災害がたくさん起きたようです。台風5号も、総雨量が400mmを超えて、三陸鉄道の線路が流されたり、道路が水没したりしました。ネットでも「こんな雨、見たことない」「避難指示が出てもどうしたらいい?」という声がたくさんあり、皆さんの不安な気持ちが伝わってきます。更に、線状降水帯による急な豪雨も問題になっています。短時間で狭い範囲にバケツをひっくり返したような雨が降って、都市部では排水が追いつかず、道路や家が水浸しになる事もよく発生しています。地下の施設が水没する事態にもなっていますね。

なんで被害がこんなにひどくなってるの?
地球温暖化の影響:
気象庁や専門家によると、地球温暖化が豪雨に大きく関係してるようです。海の表面の温度が上がると、空気中の水蒸気が増えて、強い雨が降りやすくなるんだとか。台風10号のときも、8月25日の海面水温が普段より高くて、湿った空気がずーっと流れ込んだことが、記録的な大雨の原因になったという事らしいです。
のんびり進む台風の特徴:
台風10号みたいな「のんびり進む台風」は、普通の台風と違って、動くのがとても遅いのが特徴です。通常、台風は偏西風や太平洋高気圧に押されて結構進みますが、台風10号は時速9キロ以下でノロノロでした。雨雲が同じ場所に長く居座ったせいで、局地的な大雨が何時間も続く事になったようです。気象庁は、こういう遅い台風が今後も増えるだろうと言ってますね。
都市化の影響:
都市部では、地面がコンクリートで覆われてるので、雨水を吸収する力が弱まってるといいます。だから、排水システムに負担がかかり、洪水が増えてるんだとか。東京消防庁によると、都市部の水没被害が最近増えており、特に地下道や地下施設での事故が問題になっているようです。

今すぐ準備しておきたい物と行動
台風や豪雨に備えるには、事前の準備がとても大事です。具体的に何を準備して、どう動けばいいか、まとめてみました。
準備しておきたい物
非常持ち出し袋:
飲み水(1人1日3リットルを目安に3日分)
食べ物(レトルトご飯、乾パン、缶詰とか)
懐中電灯と予備の電池
携帯ラジオ(情報ゲット用)
モバイルバッテリーと充電ケーブル
救急キット(絆創膏、消毒液、いつも飲んでる薬)
身分証明書のコピー、保険証
現金(小銭も忘れずに)
家での備蓄:
飲み水(1週間分がベスト)
食べ物(インスタントや冷凍食品)
簡易トイレ(水が止まったときに必要)
防水シートや土のう(水が入ってこないように)
ハザードマップ(避難場所をチェック)
その他の大事な物:
雨具(レインコート、防水の靴)
防寒具(夜の避難に備えて)
マスクや除菌グッズ(清潔を保つために)
事前にしておきたい行動
ハザードマップをチェック:
自治体のハザードマップで、家の周りの洪水や土砂災害の危険を調べておきましょう。NHKの災害情報マップも便利です。特に、川の近くや低地、急な斜面のそばに住んでる人は、早めに避難計画を立てておくのが大事です。
家のチェック:
屋根や外壁の補修、排水溝の掃除をして、雨水がちゃんと流れるようにしておきます。窓やドアに防水テープを貼ったり、土のうを置いたりして、水が入らないように準備しましょう。
情報をこまめにチェック:
気象庁の「防災気象情報」やNHKの速報をマメに見ておきます。Xなどの情報も参考になりますが、ホントかどうか見極めましょう。スマホに気象庁や自治体の防災アプリを入れて、警報や避難指示をすぐキャッチできるようにするとよいです。
避難の練習:
家族で避難経路を確認して、夜や停電のときのための練習をしておきます。お年寄りや子どもがいる家は、移動に時間がかかることを考えて計画しましょう。

私が実際に経験した豪雨の話:学んだこと
2023年の夏、私の住む地域がすごい豪雨に襲われました。夜中にスマホから急に緊急速報が鳴って、ビックリしたのを覚えてます。近くの川が急に増水してると知って、家族で大慌てで避難の準備を始めました。でも、ハザードマップをちゃんと見てなかったから、どの避難所が安全かわからず、かなり焦りましたね。幸い、家は水没せずに済みましたが、近所では道路が水浸しで、車が動けなくなってる光景を見ました。この経験で、事前の準備がどれだけ大事か、ほんとに実感しました。夜の避難は暗くて足元が悪いから、懐中電灯や防水の靴がないとキツいです。あと、避難所に行ったら食べ物や毛布が足りなかったので、非常持ち出し袋の準備が超重要だとわかりました。今は、家族でハザードマップをチェックしたり、防災グッズを定期的に見直したりしてます。この経験で、「備えとけば安心」と心から思いました。
災害が起きたときの行動のポイント
避難のタイミング:
気象庁の警報や自治体の避難指示を待たず、早めに動くのが命を守るコツです。「大雨特別警報」や「線状降水帯発生」の情報が出たら、すぐ避難を始めましょう。家が安全なら「家で避難」もありですが、2階以上の高い場所に移動して、窓から離れるのが大事です。
避難の注意点:
けして川などを見に行っちゃダメです。過去には、気になり見に行って増水した川に流される事故がたくさん起きてます。車で避難すると水没するリスクがあるので早めに徒歩で避難しましょう。土砂災害の危険がある地域は、夜でもすぐ避難所へいきましょう。
近所との連携:
近所の皆と情報を共有して、助け合える関係を作っておくのも大事です。お年寄りや障害者がいる家を把握して、避難の手助けができるように準備しておきましょう。

早わかり表:台風・豪雨への備え
| 項目 | 準備物・行動 |
|---|---|
| 非常持ち出し袋 | 飲み水(3日分)、食べ物、懐中電灯、携帯ラジオ、モバイルバッテリー、救急キット、現金 |
| 家での備蓄 | 飲み水(1週間分)、食べ物、簡易トイレ、防水シート、土のう、ハザードマップ |
| その他の必需品 | レインコート、防水靴、防寒具、マスク、除菌グッズ |
| 事前の行動 | ハザードマップ確認、家のチェック、情報収集、避難の練習 |
| 災害時の行動 | 早めの避難、家なら2階へ、川を見に行かない、近所と協力 |
国や自治体の取り組みと私たちの役割
政府や自治体は、豪雨災害の深刻化に対応して、いろんな対策を進めています。内閣府は
災害救助法を適用したり、激甚災害に指定したりして、被災地の復旧をサポート出来る体制を整えてるようです。気象庁は、早期注意情報や警報を段階的に出して、早めの避難を促してくれます。大きな川の氾濫は減ってるようですが、都市部の小さな川や下水道の整備はまだまだ課題のようです。私たちには、こうした情報などをしっかり使って、自分や家族やペットを守る責任があります。災害が増加してきている今、ハザードマップを見たり、防災グッズを準備したりするのはもちろん、地域の防災訓練などにも参加して、知識を増やす事も大事になってきます。

これからの展望と私たちにできること
気象庁は、今後も「のんびり進む台風」や線状降水帯による大雨が増えると予測しています。地球温暖化を抑えるには、個人個人が、節電、リサイクル、バスや電車を使うなど、
環境に優しい行動も大事になってきます。小さなことの積み重ねが、気候変動を和らげる一歩になります。防災教育ももっと強化したいところですよね。子どもたちにハザードマップの使い方や避難の大切さを教えることで、未来の防災意識を育てられます。地域の防災ワークショップなども効果的ですね。
まとめ
台風や豪雨の被害は、どんどん深刻化しています。台風5号や台風10号みたいな「のんびり進む台風」は、すごい雨量と長引く災害リスクを教訓として教えてくれました。事前の準備、情報チェック、早めの避難が命を守る鍵になります。私の豪雨体験でも、防災グッズやハザードマップの準備の大切さをとても痛感しました。
今、私たちにできるのは、個人・地域・国が一緒になって防災力を上げることです。ハザードマップを手に、家族や近所の人と避難計画を話したり、防災グッズを揃えたり、どんな大雨が来ても、冷静に対応できる準備が、家族とペットの安心な未来につながります!