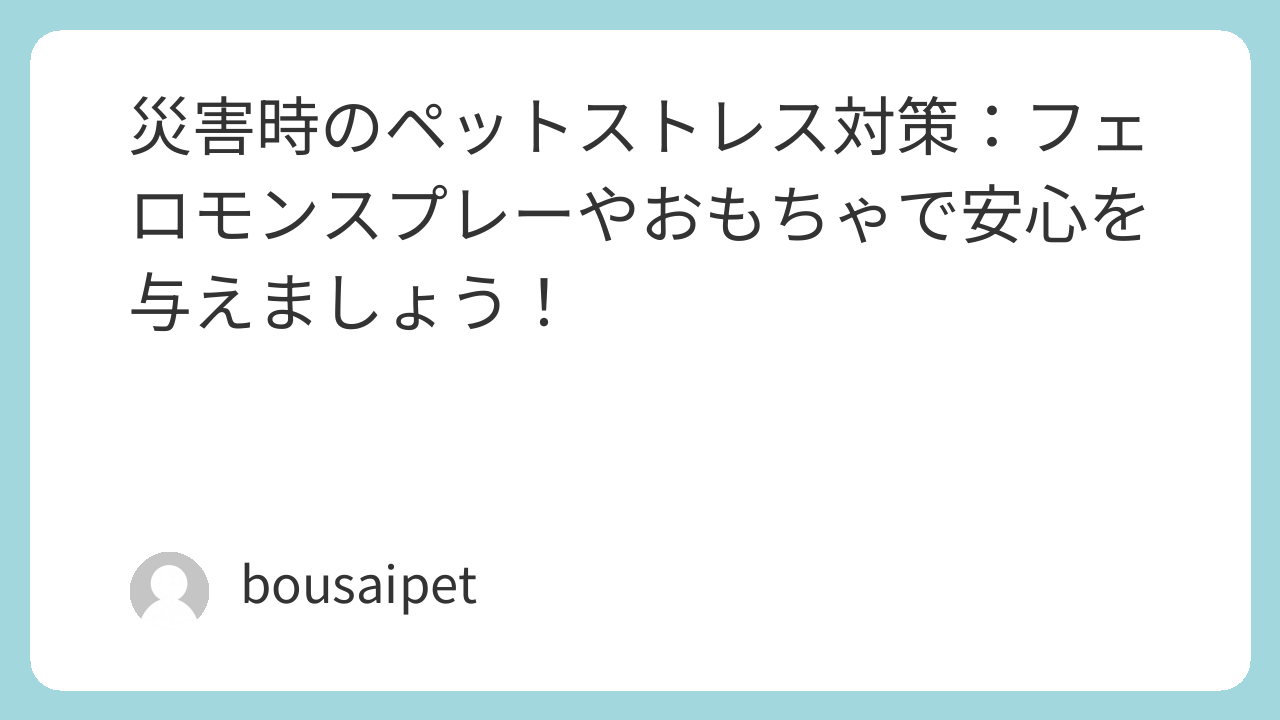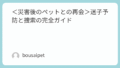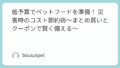災害は、ペットにとっても大きな試練になりますよね。自然災害は、ペットを怖がらせ、不安な気持ちにさせてしまいます。避難所での生活や慣れない環境は、ペットのストレスをさらに増やすことも。。今回は、災害時にペットの心を落ち着けるためのグッズやテクニックを、フェロモンスプレーとおもちゃを中心に詳しくご紹介していきます。
災害がペットに与えるストレスのリアル
災害は、ペットの心に大きな影響を及ぼします。普段とは違う環境や状況が、どんなストレスを引き起こすのか、まずはその特徴を一緒に見ていきましょう。
1.1 急な環境の変化がストレスの原因に
地震の揺れや台風の強風は、ペットをびっくりさせてしまいます。たとえば、能登半島地震では、避難所でペットが落ち着かず、ご飯を食べなくなったり、吠え続けたりしたケースがたくさん報告されました。犬はそわそわしたり、猫は隠れたり、ペットによって反応はさまざま。慣れない場所や騒音が、ストレスを増やしてしまうんです。

1.2 飼い主さんとの離れ離れが不安を大きくする
災害時には、避難の混乱や避難所のルールで、ペットと飼い主さんが離れることがあります。
こんなとき、ペットは強い不安を感じてしまうんです。特に、犬や猫は飼い主さんとの絆が深いので、離れている時間が長いとストレスがたまってしまいます。そんなときに、安心感を与えるグッズが大活躍しますよ。
1.3 ストレスが体にも影響する
ストレスが続くと、ペットの体にも影響が出てきます。猫がストレスで毛を抜きすぎて皮膚が荒れたり、犬が下痢や嘔吐をしたりすることがあります。免疫力が下がって、病気にかかりやすくなることも。。早めにストレスをケアして、ペットの健康を守ってあげましょう。

フェロモンスプレー:ペットの心を科学で癒す
フェロモンスプレーは、ペットのストレスを和らげるのに、じつは科学的にも証明されている優れたグッズなんです。災害時の不安な場面でも、ペットに安心感を届けられますよ。
2.1 フェロモンスプレーってどんなもの?
フェロモンスプレーは、ペットが自然に作り出す「安心の信号」を再現したものです。たとえば、猫用の「Feliway」は、猫が顔をこすりつけてマークするフェロモンをまねています。犬用の「Adaptil」は、母犬が子犬を落ち着かせるフェロモンに似ています。
研究によると、これらのスプレーは、吠えすぎや隠れる行動を減らす効果があるんです。なんだか、科学の力ってすごいですよね!
2.2 災害時にどうやって使う?
フェロモンスプレーを上手に使うコツを、以下にご紹介します。
避難所での使い方:
ペットのクレートや毛布にスプレーをシュッと吹きかけて、安心できる場所を作ってあげましょう。1日2~3回、製品の説明書に従って使ってくださいね。
移動中に:
キャリーバッグや車内にスプレーすると、移動のストレスが軽くなります。スプレーしてから10分くらい待つと、ペットがリラックスしやすいですよ。
事前に試す:
災害前に家で使ってみて、ペットがどんな反応をするかチェックしておくのがおすすめ。気に入ってくれるか、確認しておくと安心です。
2.3 使うときの注意点
フェロモンスプレーは、7~8割のペットに効果があると言われていますが、すべての子に効くわけではありません。とても怖がっているときは、効果が少し弱まることも。そんなときは、おもちゃや他の方法と一緒に使ってみてくださいね。
あと、狭い場所で使いすぎると、ペットの呼吸に影響するかもしれないので、換気を忘れずしましょう!

おもちゃ:遊びでストレスを吹き飛ばそう
おもちゃは、ペットの気をそらして、ストレスを軽くするのにぴったりのアイテム。災害時の環境でも、楽しく遊べるおもちゃを選んであげましょう。
3.1 どんなおもちゃがいい?
ペットの性格や好みに合わせて、災害時に役立つおもちゃを選んでみてくださいね。いくつか例を挙げますね。
インタラクティブなおもちゃ:
犬用の「コング」や猫用のパズルフィーダーは、ご褒美が出てくるので夢中になれます。
噛むおもちゃ:
犬は噛むことでストレスを発散します。丈夫なゴム製ボーンやナイロン製のおもちゃがおすすめです。
ぬいぐるみ:
猫や小型犬には、ふわふわのぬいぐるみが安心感を与えます。飼い主さんの匂いがついたものだと、さらに効果アップ!
3.2 災害時の使い方のコツ
避難所や移動中でも、おもちゃを上手に使えばペットが落ち着けます。
避難所での使い方:
音がしない、コンパクトなおもちゃを選んで、周りに迷惑をかけないようにしましょう。猫用のボールや小さなぬいぐるみがいいですね。
決まった時間に遊ぶ:
毎日同じ時間に、5~10分遊ぶ時間を設けると、ペットに「いつもの感じ」が戻って安心します。
事前に慣らす:
新しいおもちゃをいきなり渡すと、警戒しちゃう子もいます。災害前に遊んで、好きなおもちゃを見つけておきましょう。
3.3 おもちゃ選びのポイント
おもちゃは、ペットのサイズや噛む力に合ったものを選んで、壊れて飲み込まないように気をつけてくださいね。避難所では清潔さが大事なので、おもちゃはこまめに洗ってキレイに保ちましょう。遊びすぎると興奮しちゃうこともあるので、10~15分くらいで切り上げるのがベストです。

ほかにも!安心を届けるグッズたち
フェロモンスプレーやおもちゃ以外にも、ペットのストレスを和らげるグッズがあります。
組み合わせて使えば、もっと安心感を与えられますよ。
4.1 安心毛布や飼い主さんの匂い
ペットにとって、飼い主さんの匂いは最高の安心材料! いつも使っている毛布や、飼い主さんの着ていたTシャツを避難バッグに入れておきましょう。避難所では、クレートに毛布を敷いて、ペット専用の「安全ゾーン」を作ってあげてくださいね。
4.2 クレートやキャリーバッグ
クレートは、ペットにとって「自分だけの隠れ家」になります。災害前にクレートトレーニングをして、自分から入るように慣らしておくとGOOD!キャリーバッグには、柔らかいパッドを敷いて、フェロモンスプレーをシュッとすれば、移動中も安心です。

4.3 騒音をやわらげるグッズ
避難所のガヤガヤやサイレンの音は、ペットをビクビクさせる原因になります。ペット用の耳カバーや、クレートを毛布で覆うと、音を少し和らげられますよ。ただし、暑くなりすぎないよう、通気性には気をつけてくださいね。

飼い主さんができるストレス軽減のコツ
グッズだけでなく、飼い主さんの接し方もペットの心に大きく影響します。ちょっとした工夫で、ペットを落ち着かせてあげましょう。
5.1 落ち着いた態度で接する
ペットは、飼い主さんの気持ちを敏感にキャッチします。災害でバタバタしていても、穏やかな声で話しかけて、落ち着いた雰囲気を作ってあげましょう。ギュッと抱きしめすぎたり、大きな声で話すのは、逆に不安を増やしちゃうかも。
5.2 いつものリズムを守る
できるだけ、普段の生活リズムをキープしてあげましょう。たとえば、朝7時にご飯、夕方6時に散歩、といったスケジュールを避難所でも守ると、ペットが「いつも通りだ!」と感じて安心しますよ。
5.3 ペットのサインを見逃さない
ペットがストレスを感じているサイン(耳を下げたり、尻尾を振らなかったり、毛をなめすぎたり)に気づいたら、すぐ対応を。フェロモンスプレーを使ったり、おもちゃで遊んだりして、気をそらしてあげましょう。
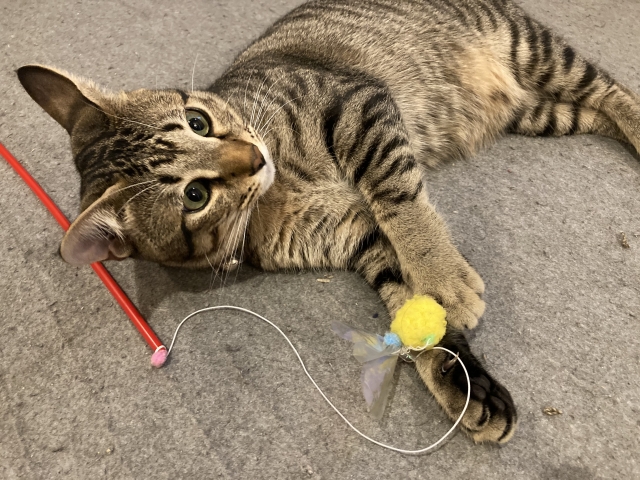
災害に備える準備をしよう
災害時のストレス対策は、事前の準備がカギ。以下をチェックして、万全の準備をしましょう。
6.1 グッズを試しておく
フェロモンスプレーやおもちゃは、災害前に買って、ペットが気に入るか試してみましょう。
スプレーを1週間使って、落ち着くか見てみるのもいいですね。おもちゃも、いろいろ試して「これだ!」というものを見つけてくださいね。
6.2 避難バッグにグッズを
避難バッグには、こんなグッズを入れておきましょう。
・フェロモンスプレー(未開封のもの1本)
・おもちゃ(2~3個、小さめでOK)
・安心毛布や飼い主さんの匂い付きアイテム
・クレートやキャリーバッグ
グッズは定期的にチェックして、期限切れがないか、壊れていないか確認してくださいね。
6.3 ストレスに強い子に育てる
普段から、ペットをいろんな環境や音に慣らしておくと、災害時も落ち着きやすくなります。
たとえば、サイレンの音を小さく流して、徐々に慣らすトレーニングが効果的。少しずつチャレンジして、ストレスに強くなるように育ててあげましょう。
災害時のペットストレス対策チェックリスト
準備をバッチリにするために、以下のチェックリストを使ってみてくださいね。
グッズの準備:
フェロモンスプレーを買って、使い方をマスターしたか。ペットが好きなおもちゃを用意したか。安心毛布やクレートを避難バッグに入れたか。
飼い主さんの対応:
ご飯や散歩の時間を決めておいたか。ペットのストレスサインを覚えたか。落ち着いた態度を意識する練習をしたか。
事前準備:
グッズを試して、ペットの反応をチェックしたか。避難バッグを定期的に点検しているか。
ストレスに慣らすトレーニングをスタートしたか。
まとめ:災害時もペットに安心を
災害時のペットのストレスは、グッズと飼い主さんの愛情でしっかり軽減できます。事前にグッズを準備して、ペットの反応を確かめておけば、災害時もスムーズに対応できますよ。さっそく、以下のステップから始めてみてくださいね!
フェロモンスプレーとおもちゃを買って、試してみる。
避難バッグにグッズを入れて、定期的にチェックする。
獣医師さんに相談して、ペットにぴったりの対策を聞いてみる。
災害が来ても、ペットと安心して過ごせるよう、今から準備を進めましょう。ペットの笑顔を守るために、できることからスタートしてくださいね!