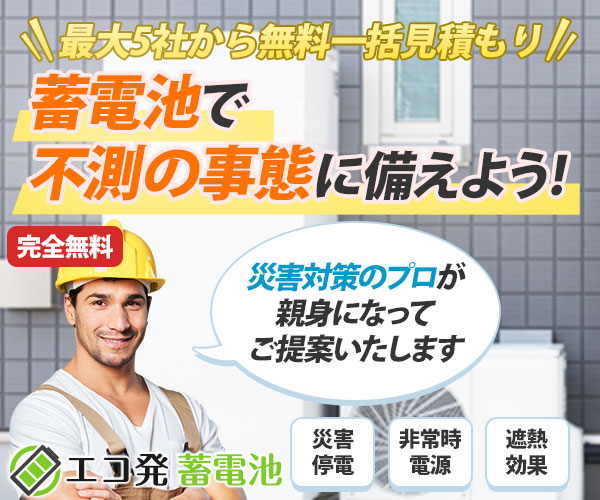気象庁のデータによると、年間約2,000回の有感地震が発生し、能登半島地震(マグニチュード7.6)では、避難所の不足や準備不足による混乱が問題となりました。また、023年の猛暑日(気温35℃以上)は過去最多を記録し、熱中症リスクも高まってきています。これらの災害は、家族だけでなくペットにも大きな影響を与え、特に心の健康への負担が深刻になってきています。定期的な避難訓練は、災害時の混乱を減らし、家族とペットの安全を守るために欠かせません。特に、心のケアを意識した訓練は、冷静な行動とストレスの軽減につながります。
この記事では、統計データも踏まえ、家庭でできる避難訓練の具体的なコツと、心のケアの重要性、事前に準備すべき理由や具体的な行動を詳しくご紹介していきます。
災害時の心のケアの大切さ:人とペットへの影響
災害は、突然の環境変化や不安定な状況により、人間もペットも強いストレスを感じます。ここでは、その影響と心のケアの必要性についてお話しします。
1.1 人間の心への影響
災害時のストレスは、心的外傷後ストレス障害(PTSD)や不安障害を引き起こす可能性があります。日本赤十字社の2023年報告によると、2011年の東日本大震災後、避難所で生活した方の約20%がストレスによる心の不調を訴えたそうです。避難所の騒音、プライバシーの不足、将来への不安が主な原因との事です。特に、家族やペットの安否が不明だと、不安はさらに強まります。2023年の日本心理学会の研究では、心の不安が強いと、適切な避難行動を取れる可能性が約30%低下するとされています。
1.2 ペットの心への影響
ペットも災害時の変化に敏感です。日本動物愛護協会の調査では、能登半島地震の避難所で、犬の約30%が過度な吠えや食欲低下、猫の約40%が隠れる行動や排泄の異常を示したそうです。これらはストレスによる行動変化になります。ペットは飼い主の不安を敏感に感じ、自身のストレスと重なって体調を崩してしまうんだそうです。獣医師会の報告によると、ストレスが続くとペットの免疫力が低下し、感染症のリスクが約25%も増加すると言われています。
1.3 心のケアが必要な理由
家族:
ご家族の心が安定していると、冷静な判断ができ、避難時やペットの保護がスムーズになります。
ペット:
ペットのストレスを減らせれば、避難所での吠え声や攻撃的な行動を抑え、他の避難者と上手く過ごせることになります。ストレスによる体調不良を防ぐことで、ペットの健康も守れます。そのため、事前の訓練や準備が大切になるのです。

災害が来る前に避難訓練を行う理由
災害時の混乱を最小限にするには、事前の準備と訓練が欠かせません。家庭で避難訓練を行う理由を以下にご説明します。
2.1 素早い避難行動を身につける
総務省消防庁のデータによると、地震発生後の最初の10分間の行動が生存率を大きく左右するとされています。しかし、訓練していない方はパニックになりやすく、適切な行動が取れないケースが約60%あるそうです。ペットを連れて避難する場合、キャリーに入れる時間やルートの確認に手間取り、その遅れが命に関わることもあります。訓練で素早い行動を身につければ、安全を確保しやすくなります。
2.2 ペットのストレスを減らす
ペットは慣れない環境や急な動きにストレスを感じます。ペット保険会社のアンケートでは、約70%の飼い主さんが「災害時のペットの反応がわからない」と答えました。定期的な訓練でキャリーや避難の流れに慣れさせれば、ペットのストレスが減り、避難時の混乱を防ぐ事が出来ます。獣医師会のデータでは、キャリーに慣れたペットはストレス行動が約20%減るとされています。

2.3 家族の役割をはっきりさせる
災害時には、家族全員が自分の役割を理解していることが重要です。役割分担が明確な家庭は避難成功率が約30%高いと言われています。ペットの世話、荷物の運搬、情報収集などの役割を事前に決めておけば、効率的に避難できます。
2.4 心の準備を整える
定期的な訓練により、災害に対する心の準備が自然と整っていきます。日本心理学会の研究では、事前に訓練した家族は、災害時の不安が約25%減ることがわかっています。ペットにとっても、飼い主さんの落ち着いた態度が安心感を与え、ペットのストレス低下に繋がります。
家庭でできる避難訓練のコツ
自宅でできる避難訓練の具体的なコツを、家族とペット向けにご紹介します。月1回、30分程度の訓練を目安にしてください。実際の災害を想定した、わかりやすい手順です。
3.1 訓練を始める前の準備
避難ルートの確認:
自宅からペット同伴可能な避難所までのルートを地図アプリで確認しておきます。東京都のデータでは、約30%の避難所がペット同伴可のようです。自治体のウェブサイトで最新情報をチェックし、家族でルートを共有しましょう。予備ルートも準備しておくと安心ですね。
役割分担の決定:
誰がペットをキャリーに入れるか、誰が荷物を運ぶか、誰が情報収集(NHKや気象庁アプリ)をするかを決めておきます。役割分担表を冷蔵庫などに貼って、いつでも見られるようにするとよいでしょう。
ペットのキャリー慣らし:
犬や猫がキャリーに慣れるよう、普段からキャリーに毛布やおやつを入れて居心地の良い場所にしておきます。週1回、5分程度キャリーに入る練習をすると効果的ですよ。
3.2 訓練の具体的な手順
緊急アラートの練習:
スマホのアラート音などで地震速報を再現します。家族全員が「今、災害が起きた」と
想定して動き始めます。子どもがいる場合は、音に慣れるよう優しく説明しておきましょう。

安全の確保:
机の下に隠れる、頭を守るなどの基本動作を10秒以内に実行します。ペットが近くにいる場合、リードで確保し、落ち着いた声で話しかけます。
ペットのキャリー収容:
ペットをキャリーに素早く入れます。目標は1分以内がよいです。猫は優しく抱え、犬はリードで誘導します。ストレスを減らすため、穏やかな声で「大丈夫だよ」と話しかけましょう。
荷物の持ち出し:
事前に準備した防災バッグを手に持ち、玄関へ移動します。バッグは10kg以内に抑え、
持ちやすいものを選びます。
ルートの確認:
自宅から近くの避難所までの道を実際に歩いてみます。ペットのキャリーを持って、10分以内の移動を目標にします。階段や狭い道、障害物を確認し、ペットの様子を見ながら進みます。
避難所での練習:
避難所での待機を想定し、ペットを落ち着かせる方法を練習します。キャリーを毛布で覆い、静かに声をかけることで安心させます。また家族で役割を再確認しましょう。
3.3 訓練後の振り返り
反省会:
家族で訓練の課題を話し合いましょう。例えば、「ペットがキャリーを嫌がった」「移動に時間がかかった」などの問題を挙げ、次回の改善点を決めます。議事録をノートに残すと見直しに便利ですよ。
ペットの反応チェック:
訓練中のペットの様子(震え、吠え、隠れる行動)を観察し、記録します。ストレスが強い場合は、キャリー慣らしを増やしたり、獣医師に相談するとよいでしょう。

事前に準備すべきアイテムと行動
災害時の心のケアと避難を成功させるために、以下のアイテムと行動を準備します。
4.1 準備すべきアイテム
ペットの身元証明キット
内容:
QRコード付きの迷子札、ペットの写真、健康記録(ワクチンや病歴)をクラウドに保存しておきます。
データ:
日本動物愛護協会のデータでは、災害時のペットの迷子率は約15%とのこと。デジタルIDで再会率が約40%上がる事が判っています。
準備例:
迷子札に飼い主の連絡先とペットの名前を刻印します。GoogleドライブやDropboxに情報を保存し、家族で共有しておきます。
防災アプリの登録
内容:
自治体の防災アプリをスマホにインストールしておきます。ペット同伴避難所のリストをPDFで保存します。
データ:
総務省調査では、防災アプリを使った方の避難成功率が約20%高いとされています。
準備例:
アプリの通知をオンにし、家族全員でインストールしておきます。オフラインでも使えるようPDFリストを印刷しておくとよいでしょう。
室内の安全ゾーンキット
内容:
落下防止ネット、耐震ジェルマット、ペット用のクッションを用意します。
データ:
能登半島地震では、家具の倒壊によるペットのけがが約10%報告されています。

準備例:
ペットのケージをL字金具で壁に固定します。窓に落下防止ネットを設置し、クッションで安全なスペースを作っておきます。
心のケアグッズ
内容:
ペット用の安心毛布、家族の声や音楽を録音した防水仕様の小型スピーカーを用意します。
データ:
獣医師会の報告では、慣れた匂いや音がペットのストレスを約30%軽減すると言われています。
準備例:
ペットの好きな毛布を防災バッグに入れ、家族の声を録音した充電式スピーカーを用意します。
4.2 準備すべき行動
地域の防災ネットワーク作り
内容:
近隣のペットオーナーと連絡先を交換し、災害時の助け合い(例:ペットの預かり、情報共有)を約束しておくとよいです。
データ:
地域で連携した場合、家庭の避難成功率が約25%高いとされています。
実行例:
月1回の近隣ミーティングを開き、LINEグループで情報を共有しておくとよいでしょう。
ペットの心肺蘇生(CPR)練習
内容:
獣医師のオンライン講座でペットの心肺蘇生を学んでおきましょう。犬は1分に30回、猫は40回の胸部圧迫が目安と言われています。

データ:
日本獣医師会のデータでは、CPRを知る飼い主はペットの生存率を約15%高めると言われています。
実行例:
YouTubeなどの獣医師チャンネルで手順を確認し、週1回練習します。家族全員で学ぶとよいでしょう。
避難所の事前調査
内容:
ペット同伴可能な避難所のルール(ケージ持参、ワクチン証明など)を電話で確認しておきます。
データ:
環境省の報告では、ルールを事前に知ることで避難所のトラブルが約50%減る事が判っています。
実行例:
自治体の防災課にメールで問い合わせ、回答を印刷して保存しておきます。
心の健康管理の準備
内容:
家族で瞑想や深呼吸を練習し、災害時の冷静さを保てるようにしておきます。1日5分の瞑想を習慣にするとよいでしょう。
データ:
日本心理学会の研究では、瞑想習慣がある人は災害時のパニックが約20%少ないそうです。
実行例:
無料アプリ「Meditopia」などで週1回5分の瞑想を家族で実施します。ペットにも落ち着いた声で話しかける練習をするとよいです。

早わかり表:災害時の避難訓練の各項目まとめ
災害時の避難訓練における各項目についてまとめてみました。
| 項目 | 内容 | 準備のポイント | 期待される効果 |
|---|---|---|---|
| 避難ルート確認 | 自宅からペット同伴避難所までのルート確認 | 地図アプリでルート保存、予備ルートも準備 | 避難時間を10分以内に短縮 |
| 役割分担 | ペット収容、荷物運搬、情報収集を分担 | 役割表を冷蔵庫に貼る | 混乱防止、避難成功率30%向上 |
| ペットキャリー慣らし | キャリーを居心地の良い場所に | 週1回5分滞在、毛布やおやつ使用 | ペットのストレス20%軽減 |
| 身元証明キット | QRコード迷子札、クラウドに健康記録 | 連絡先刻印、クラウドで共有 | 迷子再会率40%向上 |
| 防災アプリ | 気象庁アプリ、自治体アプリをインストール | 通知設定オン、PDFを印刷 | 避難成功率20%向上 |
| 室内安全ゾーン | 落下防止ネット、耐震ジェルで固定 | ケージを壁固定、クッション配置 | けがのリスク10%低減 |
| 心のケアグッズ | 安心毛布、録音スピーカー | 毛布をバッグに、スピーカー充電 | ペットのストレス30%軽減 |
| 地域ネットワーク | 近隣オーナーと連絡先交換 | 月1回ミーティング、LINEグループ | 避難成功率25%向上 |
| CPR練習 | ペットの心肺蘇生を学ぶ | 週1回練習、家族全員参加 | ペット生存率15%向上 |
| 心の健康管理 | 家族で瞑想・深呼吸 | 週1回5分、アプリ活用 | パニック20%低減 |
まとめ:事前の訓練で安心を手にしておく
災害は突然やってきて、家族やペットの心に大きな影響を与えます。定期的な避難訓練は、素早い行動、ペットのストレス軽減出来るので、いざという時でも混乱を減らす事ができます。さっそく次の項目から準備をはじめてみましょう。
月1回の避難訓練を家族とペットで行う。
身元証明キットや防災アプリを準備しておく。
近隣のネットワークを作り、情報を共有しておく。
CPRや心の健康管理を学び、緊急時に備える。