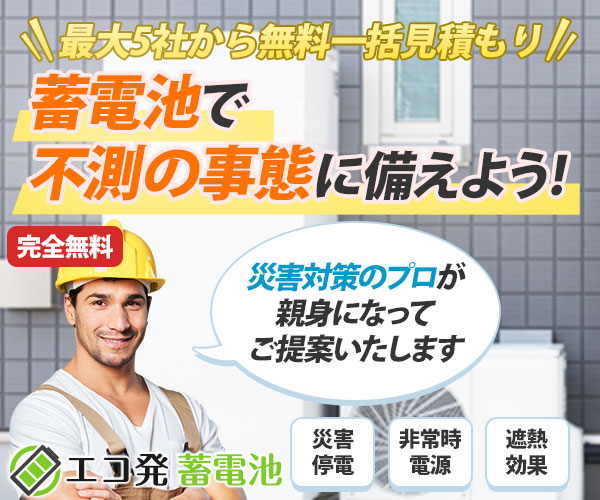災害時に蓄電池が注目されるワケ
気象庁のデータによると、2020年代も台風や地震による大規模な停電が各地で起こり、今後もそのリスクは変わりません。ネット上を見ると「停電で冷蔵庫が止まって食材がダメになった」「スマホの充電が切れて情報が得られなかった」といった声があり、電力確保の必要性が高まっています。国民生活センターによると、蓄電池に関する相談は2016年の325件から2020年には1314件に急増し、価格や設置のトラブルも増えているため、事前にしっかり準備することが大切だとわかります。
この記事では、災害時の蓄電池の役割と、なぜ今設置しておくべきかを、ネットの声も交えながらわかりやすくご紹介していきます。
災害時に蓄電池がどうして大事?
災害で電気が止まると、暮らしに大きな影響が出ます。蓄電池がどう役立つのか、具体的に見ていきましょう。
2.1 停電でも暮らしをキープ
過去の災害、例えば台風15号で千葉県の約93万戸が停電したり、東日本大震災で約466万戸が停電したりした時、電力復旧に数日から数週間かかりました。冷蔵庫が止まって食材が傷んだり、暖房や冷房が使えず快適さが失われたり、スマホの充電がなくて情報が得られなかったりしました。ネット上でも、「夜真っ暗で不安だった」「医療機器が使えず困った」といった体験談が見当たります。蓄電池があれば、冷蔵庫や照明、エアコン、通信機器を動かせて、おうちでの避難生活が楽になります。子どもやお年寄りがいるご家庭では、とくに必要性が出てくると思います。
2.2 情報や連絡手段を確保
災害時には、気象庁や自治体の最新情報をすぐに知ることが命を守るカギにもなります。
蓄電池があれば、スマホやラジオを充電して情報をすぐにキャッチする事ができます。
家族や支援機関との連絡もスムーズになり、安否確認や助けを呼ぶ際も安心です。
2.3 地域の助け合いに貢献
環境省の「避難所への再生可能エネルギー導入」事例では、千葉市や仙台市が避難所の182カ所と199カ所に蓄電池と太陽光発電を導入し、停電時でも照明や冷暖房を確保しました。おうちに蓄電池があれば、近隣の方に電力を分けたり、避難所での支援活動に役立てたりできます。ネット上でも「近所で充電できる場所がなくて困った」という声があり、蓄電池が地域の支えにもなる事がわかります。
2.4 仕事や生活の継続
個人事業主やテレワークをする方にとって、停電は仕事の継続困難、データの損失に繋がります。ALSOKの防災情報によると、蓄電池は事業継続計画の重要な一部となっており、サーバーや通信機器を動かし続けるシステムとして大役を担っています。おうちでも、パソコンやWi-Fiを動かせるので仕事を続ける事ができます。
なぜ今、蓄電池を設置するべき?
蓄電池は災害が起きてからでは遅いんです。事前に設置すべき理由をまとめておきます。
3.1 災害はいつ来るかわからない
台風や地震は突然やってきます。2020年の台風10号では九州で約48万戸が停電し、復旧に1週間以上かかりました。ウェブ上の声では「停電が長引いて準備不足を痛感した」といった後悔の声が聞こえました。蓄電池を事前に設置しておけば、急な停電でもすぐに電力を確保できます。
3.2 設置には時間がかかる
蓄電池の設置には、専門業者による現地調査や配線工事、設定が必要です。京セラの情報では、設置に数日から数週間かかるのが普通のようです。災害が起きてからでは業者が忙しく、すぐに対応できないことも。。事前に設置しておけば、そんな心配はいりません。
3.3 補助金でお得に導入
現在、国や自治体の補助金が蓄電池の導入をサポートしているようです。環境共創イニシアチブによると、補助金は最大60万円や容量3.2万円/kWhなどで、条件によって支給されます。でも、予算に限りがあるので早めの申請が大事になってきます。ウェブでは「補助金の締め切りを逃して高額になった」という声もあり、早めに動くのがお得です。
3.4 普段の電気代も節約
蓄電池は災害時だけでなく、普段の電気代削減にも役立ちます。例えば東京電力のスマートライフプランなら、夜の安い電気を蓄電池に貯めて、昼の高い電気を使うことで節約できます。
「電気代が上がって蓄電池を決めた」という方も増えたようです。

災害前に準備したい物と行動
蓄電池をフル活用するために、準備品と行動をまとめます。
4.1 準備したい物
蓄電池(家庭用):
4kWh以上の容量がおすすめです。冷蔵庫(200W)、照明(50W)、スマホ充電(5W)を
数日動かせます。200V対応ならエアコンやIHもOKです。
太陽光パネル:
蓄電池と組み合わせて、昼の電力を貯めて夜や曇りの日に使います。千葉市の避難所では太陽光+蓄電池が活躍した模様です。
EV連携システム:
電気自動車(EV)のバッテリーを家庭の電源に出来ます。長期間の停電に備える事が出来ます。
防災アイテム:
LEDランタン(電池式、予備電池付き)、携帯ラジオ、防水ポーチ(書類や充電器用)、携帯トイレ(1人1日5回×7日分)。

家電の電力リスト:
家電の消費電力(W)と使用時間をメモしておきます。例:冷蔵庫24時間で1.2kWh、テレビ2時間で0.3kWh。京セラのツールで必要容量を計算できます。
補助金書類:
身分証のコピー、住宅の証明書、業者の見積書。補助金申請をスムーズに出来ます。
4.2 災害前の行動
蓄電池選びと設置:
エコ発蓄電池のようなサービスで、信頼できる1~5社の見積もりを比較します。200V対応、自動切り替えのモデルがよいでしょう。
電力ニーズの確認:
1日の消費電力を計算してみます。4人家族ならだいたい約10kWh。災害時は5kWh以内に抑える計画を立てましょう。
自動運転モードの確認:
蓄電池の説明書を読んで、停電時の自動切り替えをチェックします。
避難所の調査:
自治体の防災マップで、蓄電池や太陽光パネルがある避難所を確認しておきます。さらに連絡先をメモしておきます。
満充電のキープ:
台風予報が出たら災害モードで満充電にします。AI付き蓄電池(電池バンク)なら天候情報を自動で取り込み、充電を最適化します。
防災練習:
家族で停電時の行動(ブレーカーオフ、蓄電池切り替え)を練習しておきます。

地域別に見た蓄電池の必要性
地域ごとの災害リスクに応じた蓄電池の使い方をご紹介します。
5.1 海沿いの地域(九州、沖縄、四国)
台風や高潮で停電リスクが高い。2020年台風10号では九州で約48万戸が停電しました。10kWh以上の蓄電池と太陽光パネルで、2週間分の電力を準備しましょう。
追加ポイント:
高潮に備え、出来れば蓄電池を2階以上に設置します。また防水ポーチで書類を保護しておきます。
5.2 都会エリア(東京、大阪、横浜)
高層ビルの強風や洪水が心配です。5kWh以上の蓄電池で照明やスマホをカバー出来るようにします。
追加ポイント:
ビル揺れに備え、蓄電池を固定しておきます。コンパクトなモデルを選ぶと良いでしょう。
5.3 内陸エリア(岐阜、奈良)
土砂災害で電線が切れるリスクがあります。防災マップで危険箇所を確認し、6kWh以上の
蓄電池で自宅避難を計画します。

追加ポイント:
土砂災害警報に注意し、早めの充電をしましょう。
5.4 豪雨が多い地域(中国地方、東北)
長期間の雨で復旧が遅れる可能性があります。防水設置の蓄電池(2階以上推奨)と、密閉容器で予備品を保護しておきましょう。
追加ポイント:
湿度で機器が傷まないよう除湿剤を活用するとよいでしょう。
蓄電池導入のポイントと注意点
6.1 導入のポイント
容量と出力の選び方:
4~10kWhの容量、3~5kWの出力が目安です。エアコン(1000W)やIH(1500W)を使うなら200V対応を選びましょう。
補助金の活用:
DR補助金(最大60万円)や東京都の助成金を申請します。早めの申し込みで予算を確保しておきましょう。
信頼できる業者:
エコ発蓄電池で複数見積もりで比較します。
太陽光パネルとの組み合わせ:
節電と災害時の電力を両立させます。
6.2 注意点
設置場所:
通気性と防水性を確保します。2階以上設置で水害リスクを減らします。
メンテナンス:
定期点検で過充電や液漏れをチェックします。リチウムイオン電池が安全です。
災害時のリスク:
蓄電池が水をかぶると感電の危険性があります。専門業者に点検をお願いしましょう。

早わかり表:状況毎の蓄電池対策
状況毎の蓄電池対策を表にまとめてみました。参考にしてみましょう。
| 状況 | 準備品 | 行動 | 地域別ポイント |
|---|---|---|---|
| 事前準備 | 蓄電池(4kWh以上)、太陽光パネル、EV連携 | 見積もり比較、補助金申請、電力計算 | 海沿いは10kWh以上 |
| 災害接近時 | 防水ポーチ、LEDランタン、満充電 | 自動運転確認、避難所連絡先メモ | 都会は階段ルート確認 |
| 災害後 | 携帯ラジオ、携帯トイレ | 被害チェック、業者点検依頼 | 豪雨地域は防水設置 |
まとめ:蓄電池で災害に備えて安心を
蓄電池は、災害時の停電から暮らしを守る大事な設備となります。冷蔵庫や照明、スマホを動かし、おうちでの避難生活を支えてくれます。万が一に備え設置しておけば、急な災害にもすぐ対応できます。補助金でお得に導入出来、普段の電気代も節約できます。
さっそく以下の項目をから準備を始めてみましょう。
蓄電池選び:4kWh以上の容量、200V対応、自動切り替えモデルを選び、エコ発蓄電池で
信頼できる業者から見積もりを取る。
電力ニーズの確認:家電の使用時間を計算し災害時は5kWh以内に抑える計画を立てる。
補助金の申請:国や自治体の補助金を活用し早めに申請する。
太陽光パネルとの連携:長期間の停電に備え電力自給率をアップさせておく。